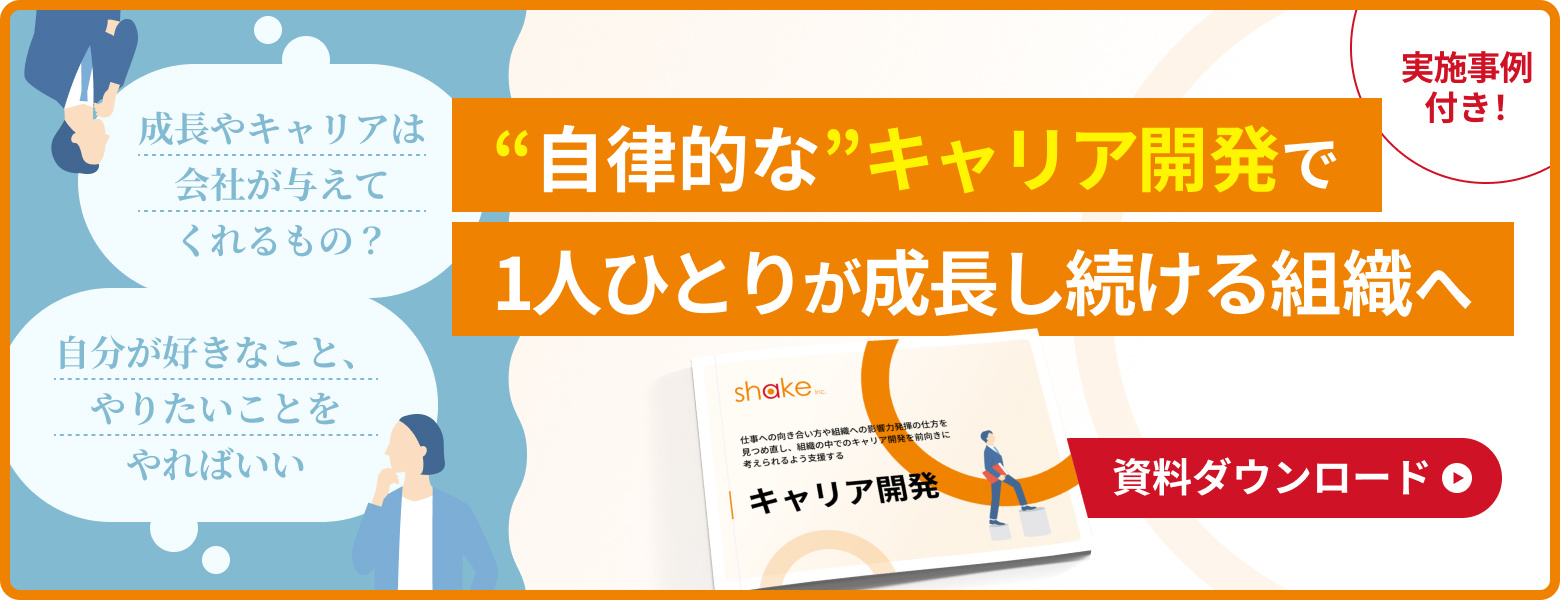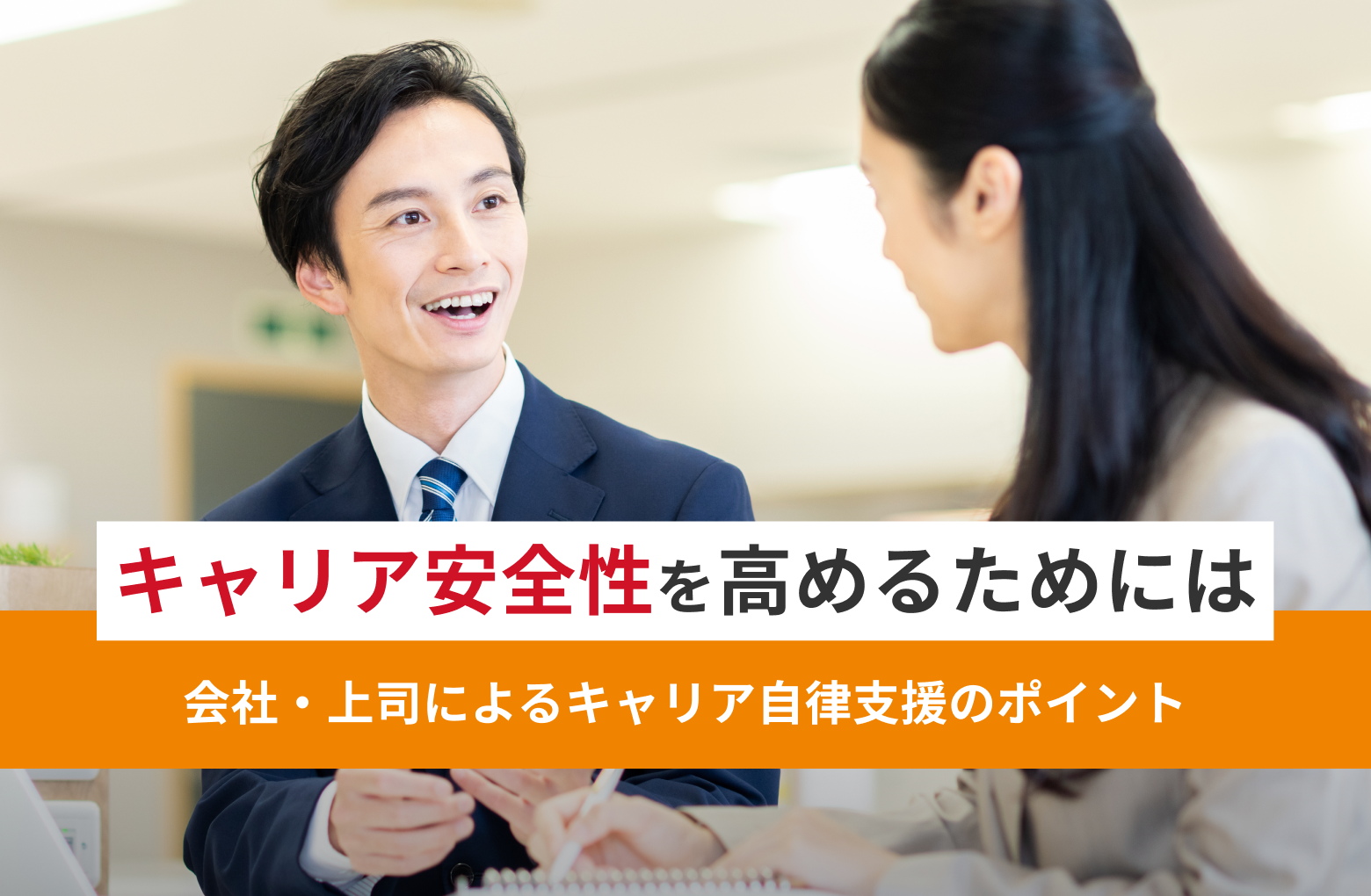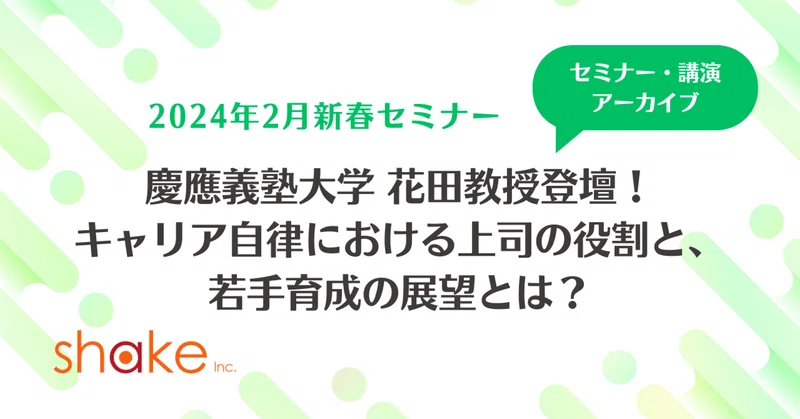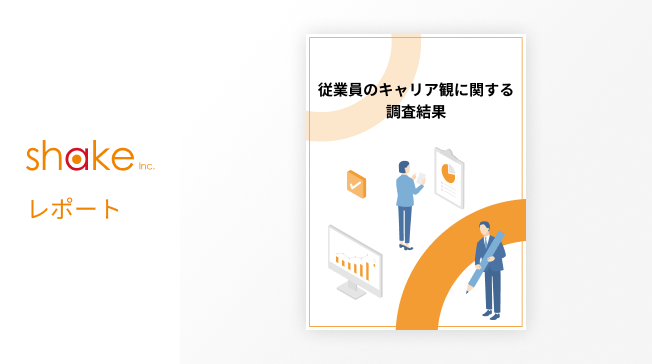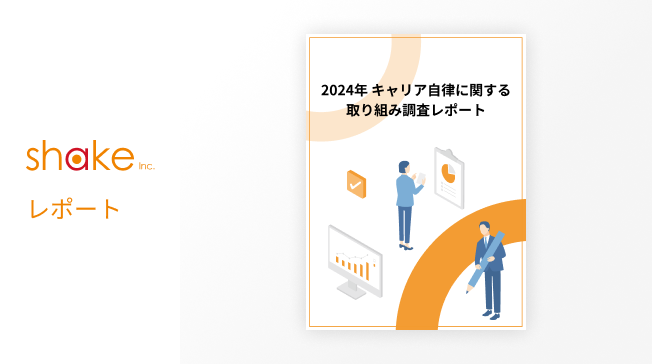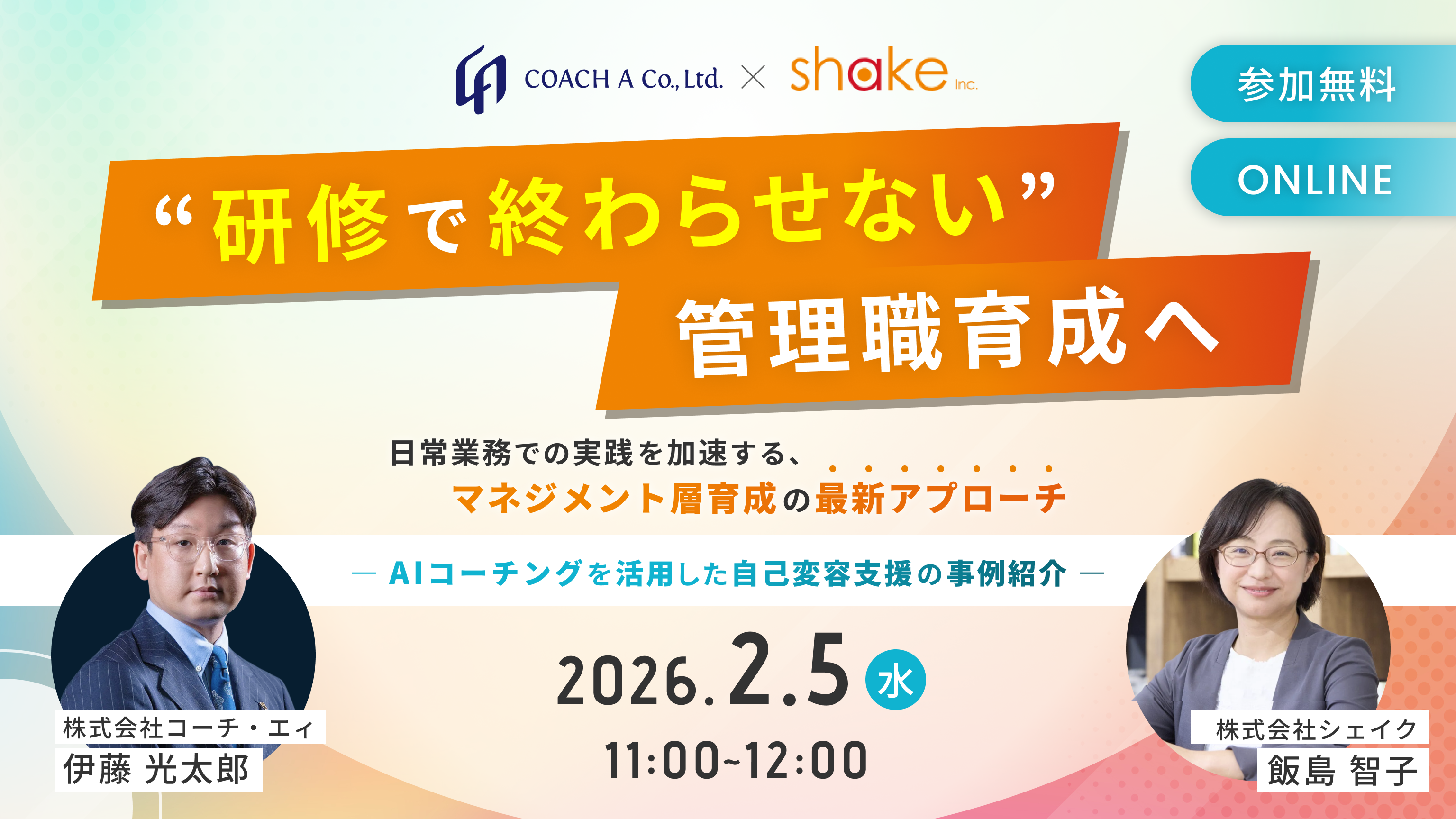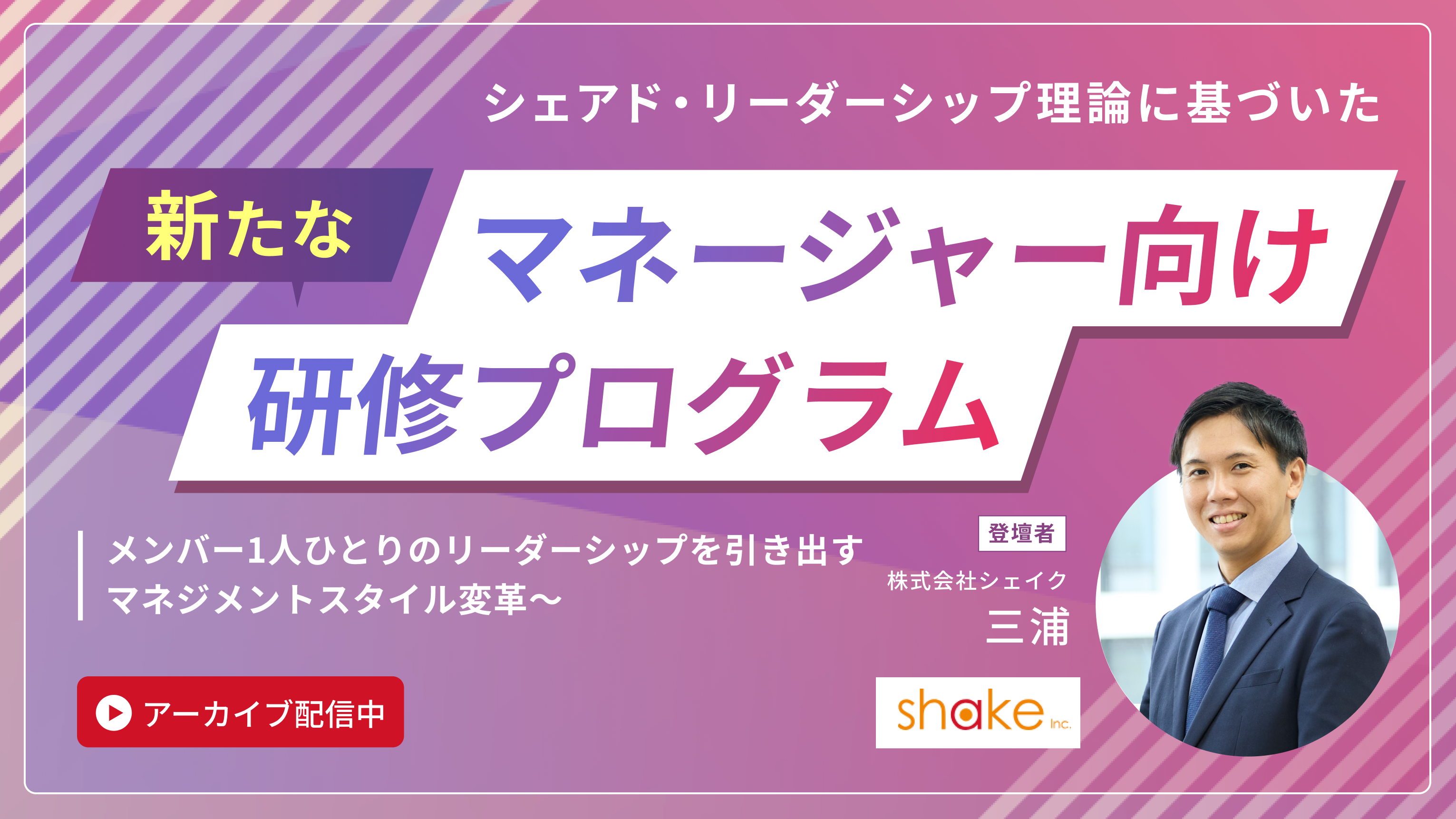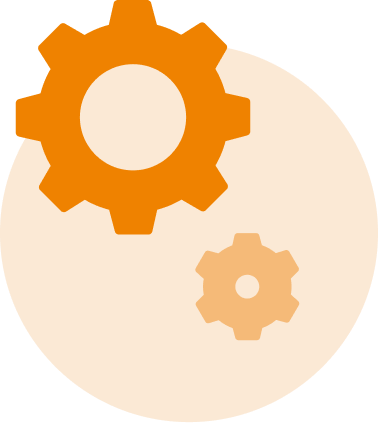皆さん、こんにちは。シェイク松林です。
今回のキャリア自律コラムでは、「若手社員×人事による個別面談支援の仕組みづくり」の実践例をご紹介します。
昨今、「優秀な若手が辞めていく」「メンタル不調者が増えている」「研修などの全体支援には限界がある」といった悩みを抱える企業が増えています。
こうした課題に対し、ある企業様と共に、人事担当が若手社員と“1対1”で向き合い、個別面談の中で成長を支援していく仕組みを構築しました。
本コラムでは、一般的な人事面談を一歩発展させた工夫やこだわり、その効果についてご紹介します。
若手社員の成長やキャリア自律支援に取り組むうえでのヒントになれば幸いです。
なぜ若手社員との個別面談の仕組みを作ったのか
きっかけは、ある企業様からの相談でした。
「新卒の離職率はそれほど高くない。でも“優秀層”ほど辞めてしまう。なぜだかわからない。」
同社では、研修やエンゲージメントサーベイを実施していましたが、個々のリアルな状態、キャリア意向は把握できていませんでした。
そこで「もっと個別に状況を把握し、配置を含めた本人に合った成長・キャリア支援が必要ではないか?」という仮説のもと、人事担当による1対1の個別面談の仕組みを立ち上げるプロジェクトが始まりました。
ただし、当初から順調に進んだわけではなく、以下のような点を慎重に検討しました。
- 優秀層を選抜して行うのか? それとも年次単位で全員を対象にすべきか?
- 個別面談は必須か?希望制か?
- 面談の位置づけや目的をどう定義するか?
- 年次あたり100名以上の新卒社員がいる中で、どう運用するか?
議論を重ねた結果、以下の方針に決定しました。
- 業務量が増え、視野が狭まりがちな特定年次の若手社員「全員」に対して
- 人事が上司・OJTトレーナーとは異なる“斜めの立場”として、若手社員の精神支援、自律に向けた土台作りを個別支援する
どんなステップで仕組みを立ち上げ、何をしたのか
対象者と本施策の目的の決定
インパクトが大きくなりそうな対象層を選定し、支援方針を議論。選抜ではなく、ある年次の若手社員「全員」を対象とする方針としました。
面談者の選定と体制作り
100名超の社員に対して育成担当だけでは対応が難しいため、採用・制度・労務担当など人事部全体で対応することになりました。
個別面談の目的、Goal設定
面談対応する方の経験値(キャリア支援の知識や面談経験など)と、若手社員の状況を踏まえて、個別面談の目的を「キャリア支援」には設定せずに、その土台となるような「精神支援・成長支援」「個別の状態把握」を目的にし、Goalを以下に設定。
<若手社員のGoal>
- 安心感を持ち、職場では相談しづらいことを相談したい相手として人事を認識している
- モヤモヤや不安を共有し、気持ちが軽くなっている
- 自身の成長や課題が整理され、今後のアクションが明確になっている
<人事施策としてのGoal>
- モチベーション状況や離職リスクを個人単位で把握し、必要に応じて現場介入、人事支援ができる
- 若手社員の状況を可視化し、採用・育成・配置のPDCAに活かせる
面談プロセス設計と人事向け研修
面談の質を担保するため、面談プロセスを標準化・マニュアル化。人事向けの研修を実施
定期的な振り返りMTG
- 面談のPDCAが回るように、面談を実施した人事担当が定期的に集まり、振り返りMTG
- 若手社員の状況を共有し、現場介入や人事支援の要否を検討。必要に応じて現場介入して支援
面談後の若手向けアンケートで効果検証
若手社員からのフィードバックを収集し、支援の効果や今後の改善点を分析
面談終了後の人事向けフォローアップ研修
面談を通じて理解した若手社員のリアルな状況の可視化と、人事部や、各々の人事領域での改善施策の明確化
個別面談の仕組みで大事にした3つのポイント
今回、個別面談の仕組みを作る中で、1対1の個別面談でできる支援に限りがある事を前提に置きました。
面談で元気になったとしても、それを阻むような組織的要因があり、だからこそ個人面談内だけでの支援に留めず、組織的な支援に発展させていく必要があると考えました。
具体的には以下のように「個別面談での支援」と「組織的な支援」が両立できるような仕組みを工夫して構築しました。
若手社員の状況を、1人ひとり定量化し、全体感を可視化する
面談した若手社員の状況を、人事担当の主観でも良いので定量化し、面談で得られた情報を組織的な支援や、人事施策のPDCAに繋げていけるように工夫しました。
- 若手社員のモチベーション状況
- これまでの経験を通じた成長実感度合い
- 会社や上司からの期待役割の認識度合い
- 今後に向けた成長期待度合い、未来に向けた改善期待度合い
- 離職リスク
- 現場介入・人事支援の要否
などを定量化し、面談を実施した若手社員の全体傾向と、気になる方が可視化されるように工夫しました。
「今年の○年目社員はこうだよね」という曖昧な把握ではなく、若手社員の状態を定量的にも可視化し、経年変化を見ることができる状態にしました。
必要に応じて現場介入や人事からの支援ができる状態をつくる
守秘義務を重視しすぎると1対1の面談内での支援に留まりがちですが、必要に応じて若手社員に「了解」を取って、現場に介入したり、人事としての支援施策を講じることを面談プロセスに組み込みました。現場介入するケースはほぼありませんでしたが、守秘義務を大切に一切介入しないことを前提にした施策ではなかった為、一部の離職リスクの高い若手社員と現場の間に入って調整できました。
人事部全体で横断的に課題を検討する仕組みをつくる
大手企業ともなると、新卒採用担当や人材育成担当などの縦割が強くなりますが、可視化した若手社員の状況を踏まえて、1つ視座を上げて、各担当領域が連携して人事部としてどのような改善を行っていけると良いか?を議論する機会を設けました。現場の実態、起きている問題を踏まえながら、視座を上げ、人事のプロフェッショナルとして人事施策を再検討する機会となりました。
個別面談の仕組みを運用した効果
興味関心を起点とした「楽しい学び」の体験をデザインする
本施策の実施を通じて、以下のような効果が見えてきました。
若手社員にとっての効果
①若手社員が自身の現状を整理し、自身や業務を捉え直す機会になった
- 若手社員が、自身の感情やモヤモヤを共有できる機会になり、気持ちが整理される機会となった
- 自身の現状(成長した事や課題)を理解し、成長や成果に向けたアクションが明確になった、業務への意味づけができた
②若手社員にとってフラットに相談できる相談先が増えた
③会社に意見・要望を伝える機会が開かれていることに安心感を感じていた
人事部にとっての効果
①人事と現場との距離感が縮まり、現場に寄り添って支援する意識が強くなった
若手社員に対するアンケートを見ると、思っていた以上に、人事と面談をすることに抵抗はなく、斜めの存在として話ができることがありがたいという声が多かった。その声もあり、人事の方にとって、現場と密にコミュニケーションをとって支援していくことのハードルが下がり、現場に寄り添った支援への意識が高まったように感じました。
②若手状況と組織課題を可視化し、人事施策としてのPDCAを回す機会になった
面談した結果を人事担当同士で共有し、若手社員の状態と、その状態の原因となっている組織課題を分析していった所、若手社員の問題だけでなく、新卒採用時のコミュニケーション問題や、上司のマネジメントスタイルが起因した問題など、様々な組織的な問題が見えてきました。人事部として、今後、何にテコ入れをしていくべきか、人事施策の課題設定する機会となりました。
③離職リスクの高い社員への支援が行えた(個別把握・支援、必要に応じた現場介入)
現場介入する機会はほぼありませんでしたが、一部の方で、現場の上司と若手社員とでコミュニケーションの齟齬が起きていて、離職リスクが高まっている状態でした。本来はお互いに解決すべき点だったかもしれませんが、多少の情報提供を現場にすることで、その誤解はなくなり、前進に向かうことができました。
最後に:本仕組み作りをご一緒させて頂いた感想
まず、本施策をご一緒させて頂いた企業様、貴重な機会をご一緒させて頂き、誠にありがとうございました。
研修で全体にアプローチした方が効率的かもしれません。ただ、その中でも1人ひとりに向き合い、支援する仕組みを作られたことは、個人的にとても意義のある一歩だったのではないかと思います。若手社員の離職防止や自律の土台作りに即効性のある施策かというとそうではないかもしれませんが、今回のように現場の1人ひとりに寄り添って支援する人事の方がいることは、会社としての求心力を高めることに繋がると感じました。「現場のこと、自分のこと、自分の成長を真剣に考えてくれる人事」がいることは、若手社員にとってとてもありがたいことだと思うからです。100名以上の若手社員を人事内で分担して面談することは大変だったかと思いますが、この取り組みの効果を更に大きくしていけるような仕組みに、共にブラッシュアップしていけたら幸いでございます。
最後に、この取り組みをご一緒させて頂く中で、効率も大事で工数調整は必要かと思いますが、1人ひとりを大切な人として見て、現場に寄り添った人事サービスを作り込んでいくことの重要性や意味を感じる機会となりました。その方が、現場と良い信頼関係、共創関係を築けるのではないかと感じました。今後も同社のような人事サービスを各社様と一緒に作っていけたら幸いでございます。
以上、本コラムが、貴社におけるキャリア自律施策の推進の一助になれば幸いです。