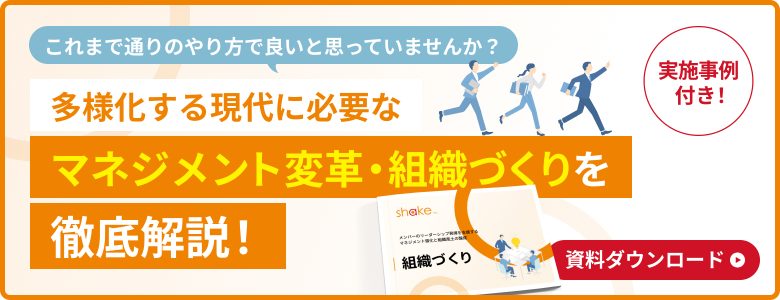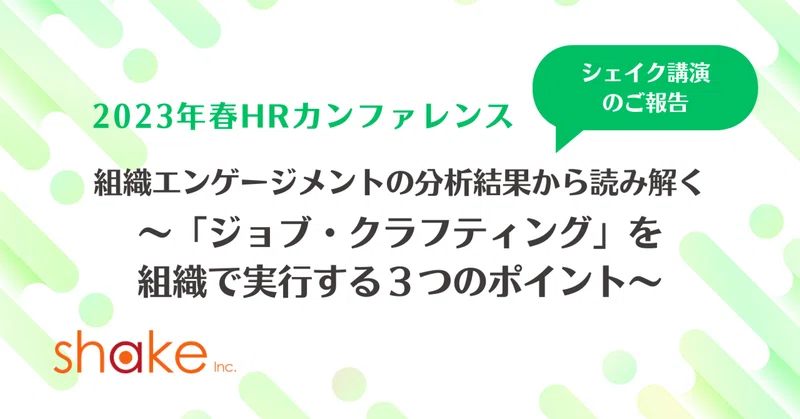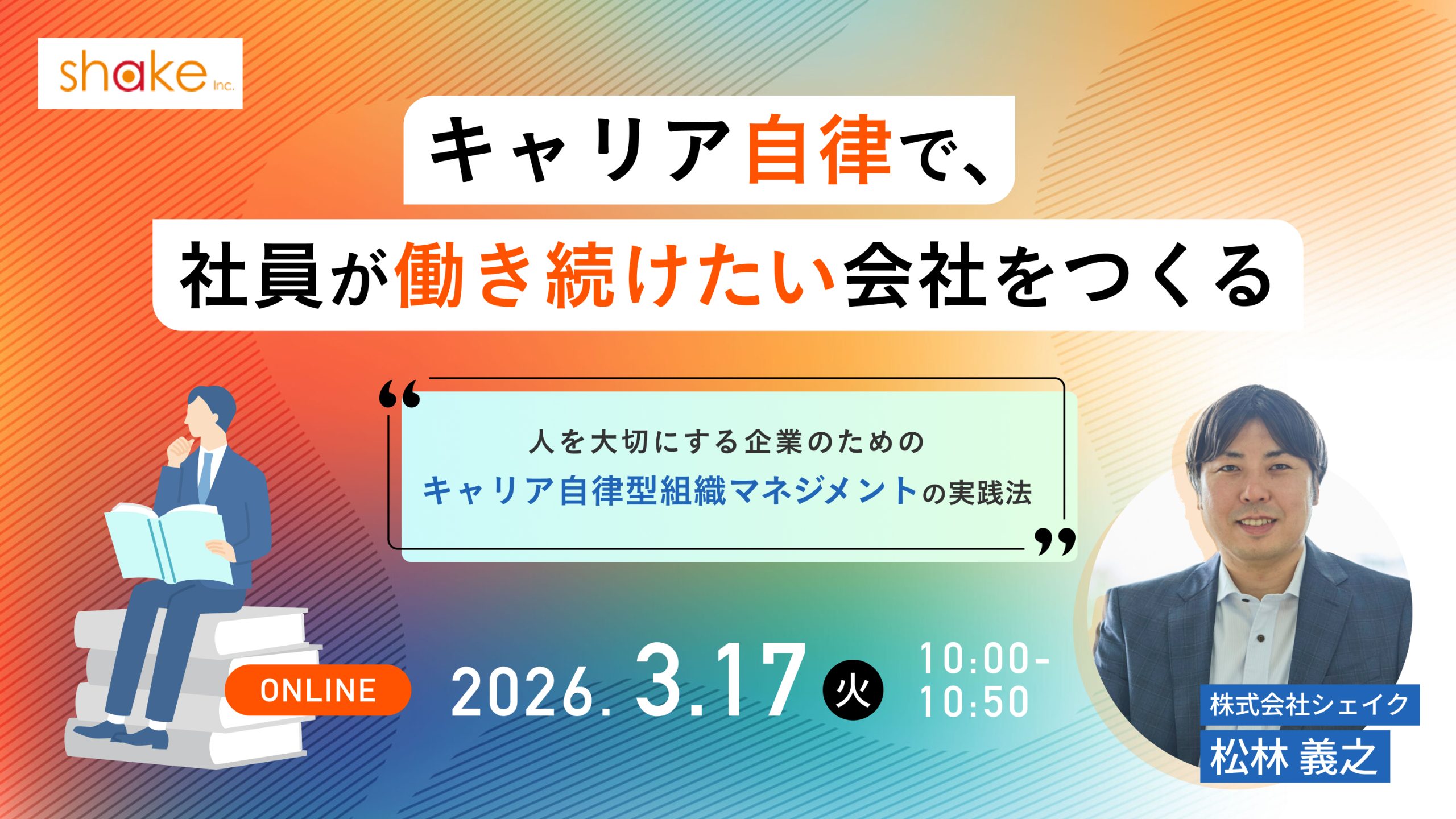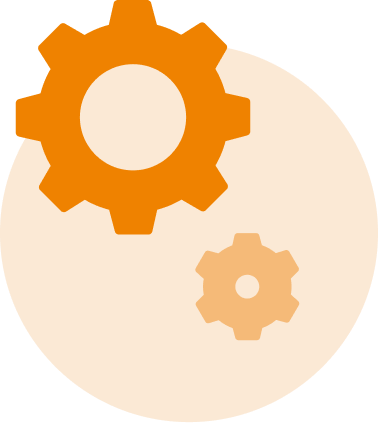こんにちは。シェイクの吉田です。
シェイクは、「誰もがリーダーシップを発揮し続ける社会」の実現を目指しており、私たち自身もその姿を体現する組織でありたいと考えています。
今回のコラムでは、そのような組織の実現に向けて、シェイクが取り入れている仕組みの一部をご紹介します。
毎年ガラガラポンする組織
シェイクの決算は8月で、新しい期は9月に始まります。期末が近づく7〜8月になると、社内は毎年のようにざわつき始めます。というのも、次の期に向けて組織体制が大きく見直され、リセットされるからです。
6月には、経営陣が全社員と面談を行い、来期に向けた希望や意向を丁寧にヒアリングします。「後輩指導に興味があり、チームリーダーに挑戦してみたい」「今期はチームリーダーを経験したが、来期は別の役割に挑戦したい」「プログラム開発に力を入れたいので、関連業務に携わりたい」といった声が寄せられます。
こうした個々の意向をもとに、経営やマネジメントメンバーが集まり、翌期の組織体制やチーム構成をゼロベースで設計します。
同時に、組織課題に横断的に取り組むタスクフォースやプロジェクトも新たに立ち上げられます。たとえば、「新卒採用タスクフォース」「価値観浸透タスクフォース」「キャリアプロジェクト」などがあり、これらは通常業務とは別に、1年間で完結する取り組みです。
つまりシェイクの組織は、通常業務も、プロジェクトも、1年ごとにゼロベースで見直される、いわば「ガラガラポン型組織」なのです。
正直なところ、この仕組みの運用にはかなりの手間と時間がかかります。毎年チームメンバーが変わることで、関係構築や役割分担のやり直しが必要になり、一時的に組織の効率が下がることもあります。「やっとチームがうまく機能してきた」と感じた頃に振り出しに戻るような感覚になる人もいるかもしれません。
それでも、私たちがこの仕組みを採用し続けているのは、ある考えに基づいているからです。
組織とは、機械か、生命体か
マネジメントをしていると、成果の最大化が強く求められます。そのためには「最適解」を追求したくなりますし、その気持ちは私もよく理解できます。成果が出なければ、組織は疲弊し、人がイキイキと働くことは難しくなります。
しかし私は、組織図をつくる際に「枠に人を当てはめる」ことに少し違和感を覚えていました。もちろん、組織パフォーマンスの最大化は重要ですが、「成果のために人をはめ込む」という発想には、どこか機械的な冷たさを感じてしまうのです。
組織は人の集まりです。もっと有機的で、自由度が高く、個々の可能性が自然と引き出されるような構造はできないかと考えてきました。人が枠に当てはめられるのではなく、人の集まりによって組織が形づくられるようなイメージです。その方が、個性が活かされ、組織にも生命力が宿るように感じています。
組織が固定化・硬直化してしまうと、人は成果だけを追う“マシーン”のようになってしまいかねません。私は、組織とは成果を生み出すと同時に、人の成長と可能性を解放する存在であるべきだと考えています。
こうした考えのもと、多少の非効率を許容しながらも、思考の硬直化を防ぎ、創造性の発揮や共創につながる「ゆらぎ続ける組織」を志向するようになりました。
この仕組みで見えてきた効果
実際にこの仕組みを運用してみて、特に大きく感じている効果が2つあります。
1.組織に対する当事者意識が高まる
毎年、自分の意志を表明して組織が構成されるプロセスを繰り返す中で、「組織に使われる個人」から「組織をつくる個人」への意識の変化が生まれています。
来期に自分は何を担いたいかを考えることで、組織への当事者意識が自然と高まり、チームのマンネリ化防止や活性化にもつながっています。
2.キャリアに対する当事者意識が高まる
もうひとつの効果は、自分のキャリアや能力開発への向き合い方が深まることです。
少なくとも年に1回、自分の意向を言語化する機会があることで、自身のキャリアについて考える習慣が育まれます。中には「まだ意向がはっきりしていない」と相談してくる人もいますが、それも問題ありません。そのような揺らぎも含めて、自分の成長と向き合う機会があること自体に価値があると考えています。
もちろん、全員の「やりたいこと」がすべて叶うわけではありません。組織の事情により、要請を優先する場面もあります。しかし、可能な限り個人の意向を尊重し、組織の現状とすり合わせながら調整するプロセスを大切にしています。
その過程では、組織図を書き直し、意向を再確認し、まるでパズルを繰り返すような作業になりますが、この「意向を聞くところから始まるプロセス」こそが、私たちにとって大きな意味をもつのです。
組織を活性化させる「仕組み」とは
今回は、シェイクが実践している組織づくりの一端をご紹介しました。この仕組みがすべての組織に有効であるとは限りません。それぞれの組織に合った方法があるはずです。
しかし、上意下達のマネジメントが機能しにくくなり、新たな価値が生まれにくくなっている今の時代、組織に「ゆらぎ」を与え続けることはますます重要になってくると思います。
皆さんの組織にとって、意味ある「ゆらぎ」とは何でしょうか?