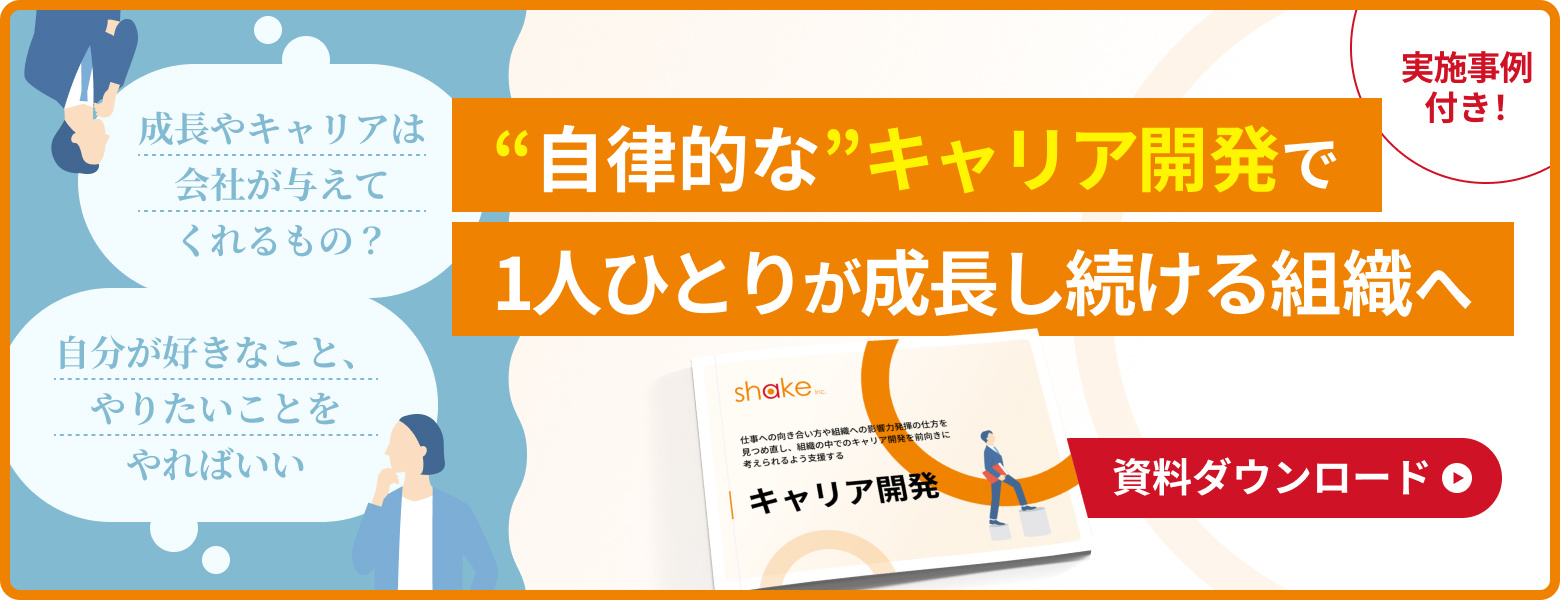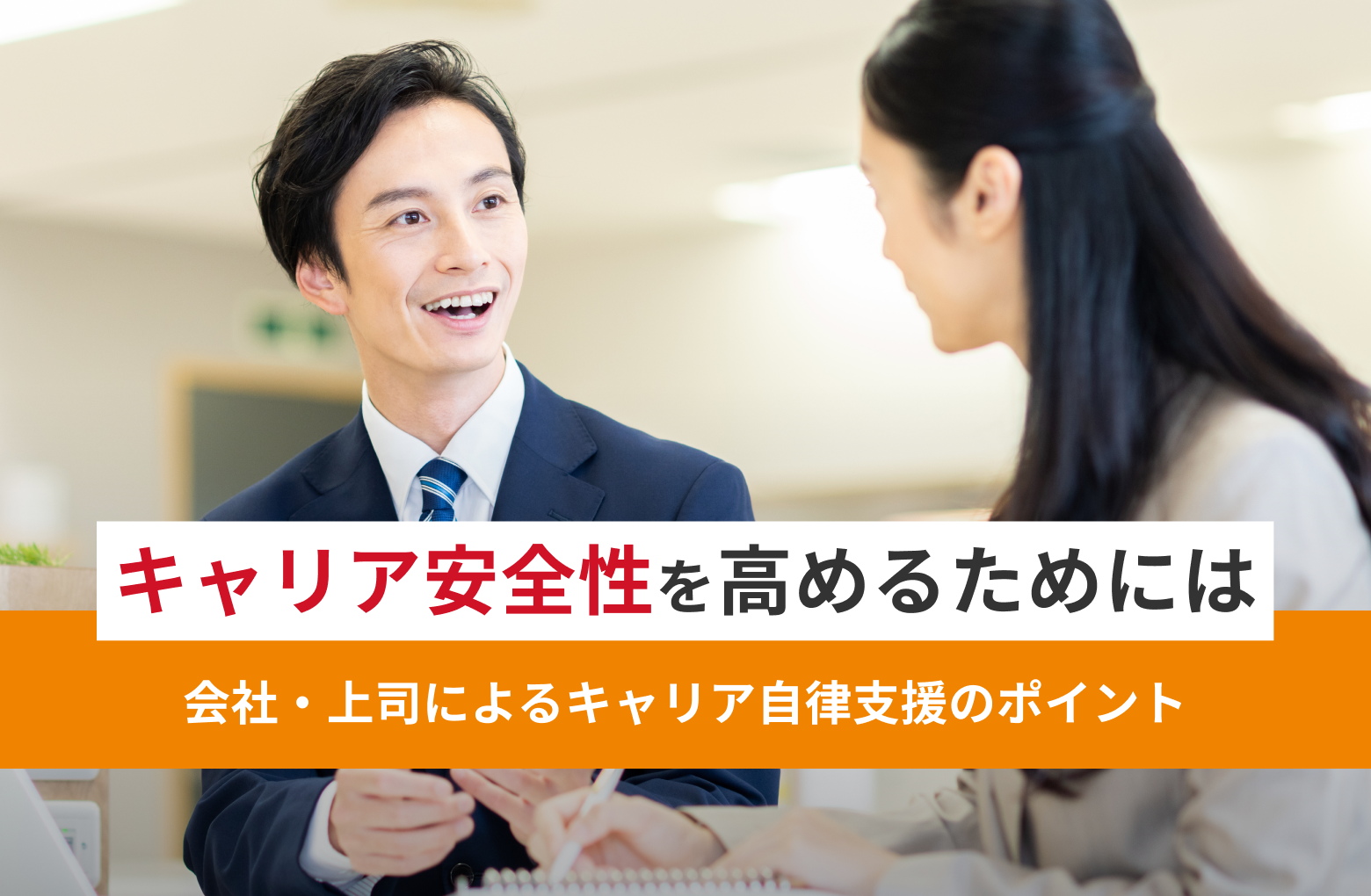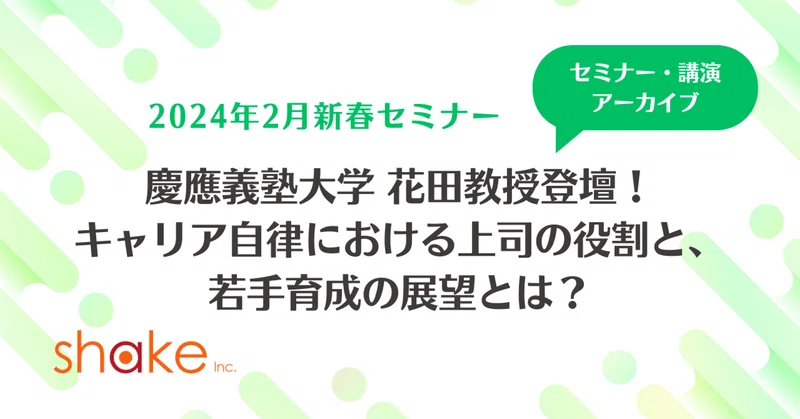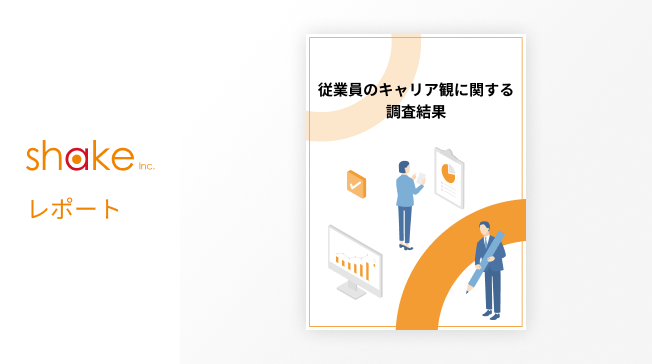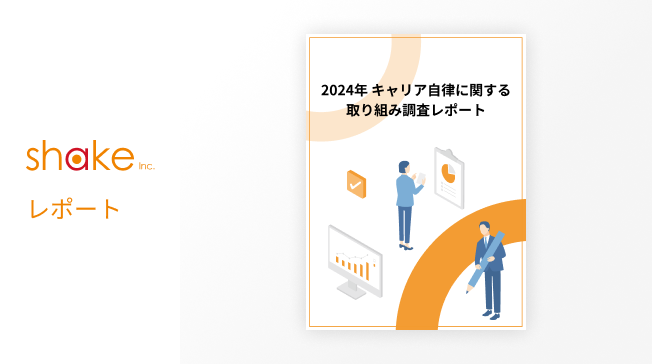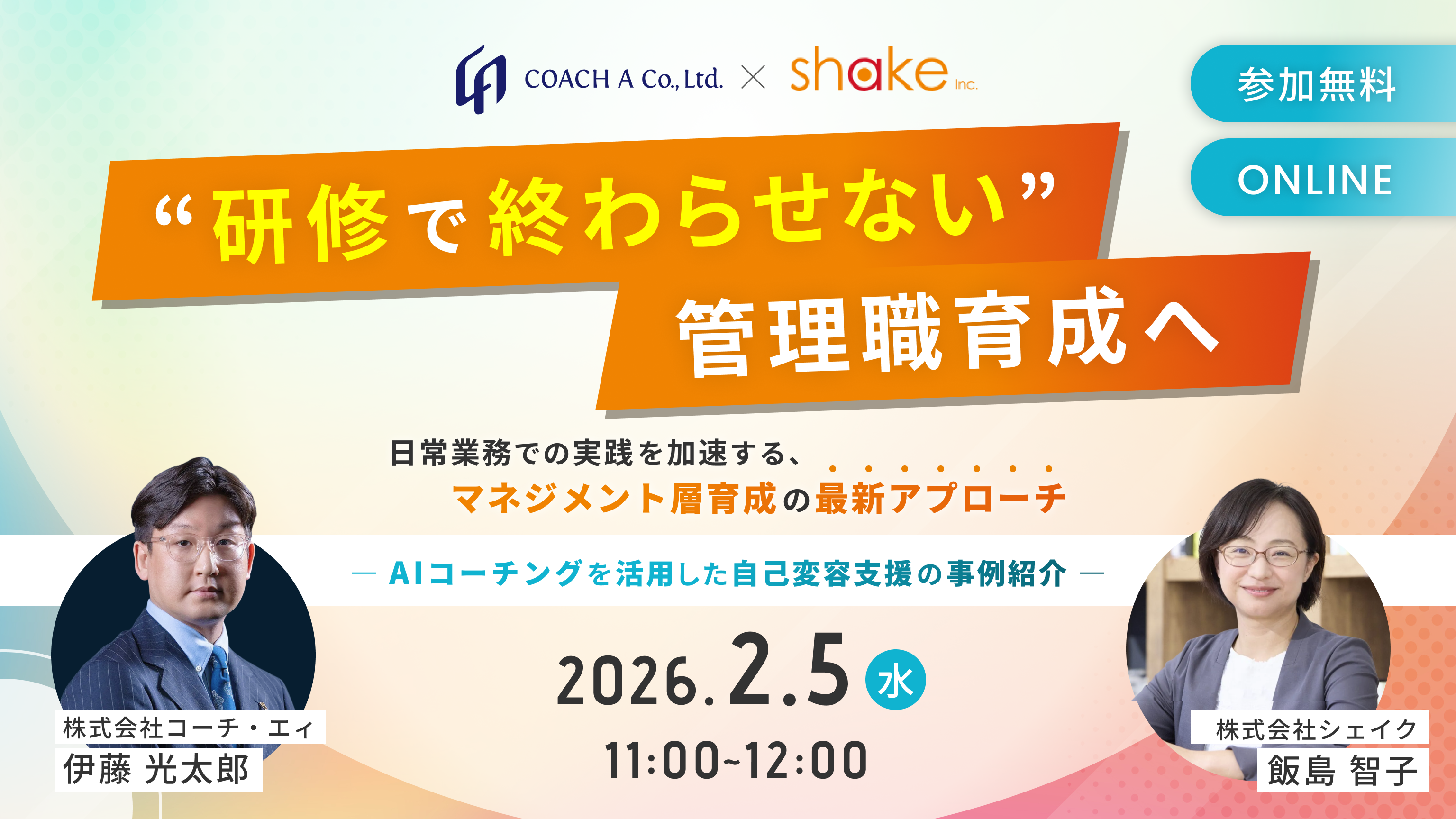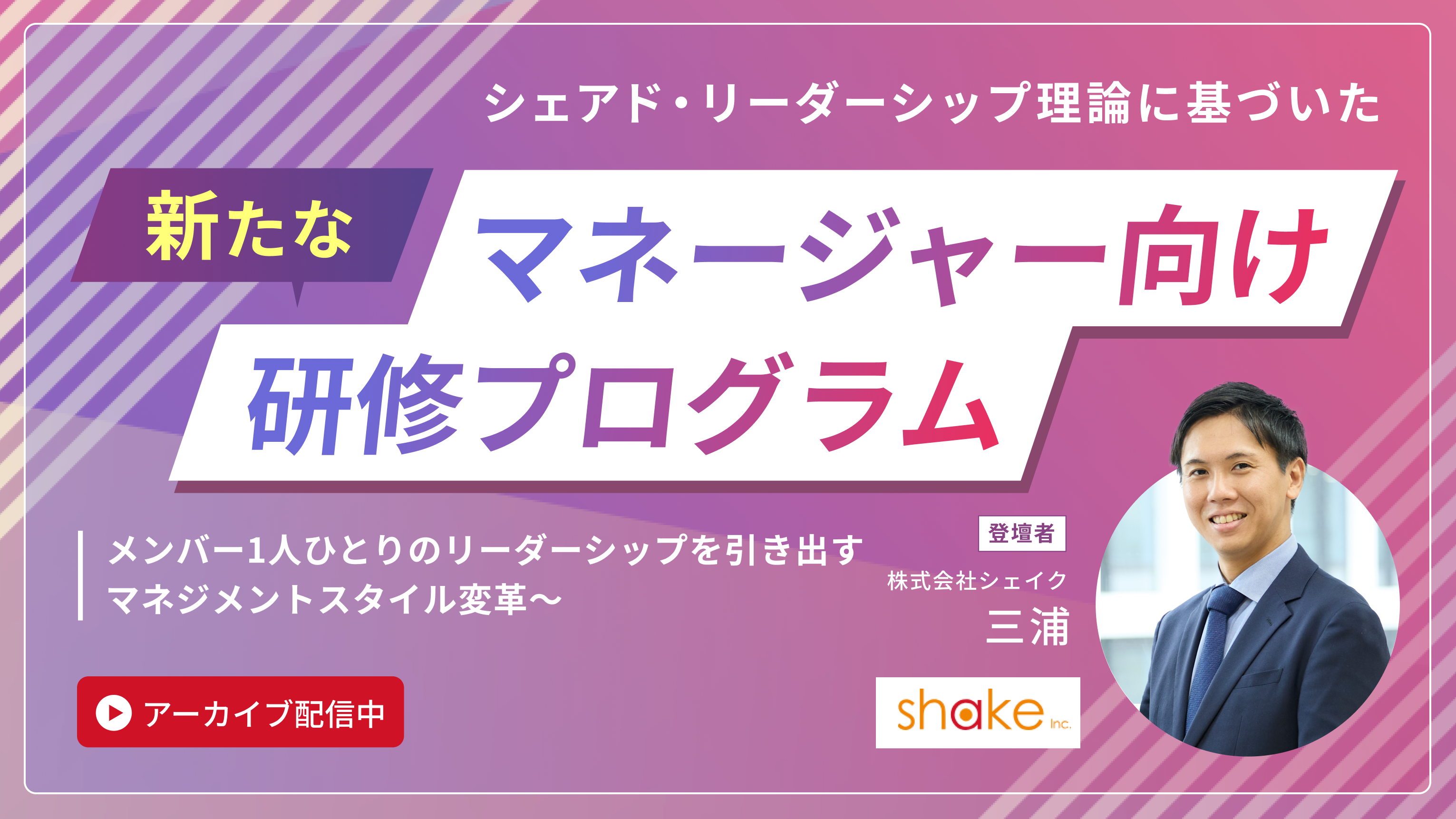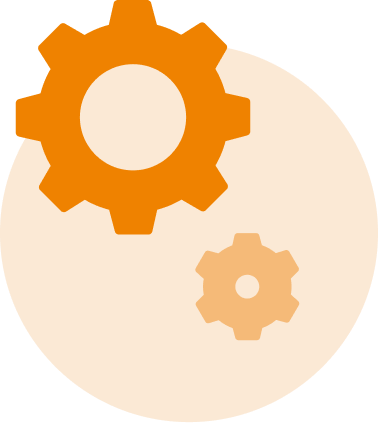皆さん、こんにちは。シェイク松林です。
今回のキャリア自律コラムのテーマは「若手社員のキャリア自律」です。
これまで、社員のキャリアは会社が決めるもの、という考えが一般的でした。しかし、最近では職業能力開発促進法の改正や、企業のキャリア支援に対する考え方の変化もあり、会社は社員のキャリアを尊重・支援する立場に、そして、社員自身も「自分のキャリアは自分で築いていくもの」という意識を持つことが求められるようになっています。
とはいえ、「キャリアを自分で考えなければいけない」と言われると、不安を感じる人も少なくありません。
今回は、ある企業で実施した若手社員向けのキャリア自律研修を参考にしながら、若手社員のキャリア自律を後押しするポイントを考えていきたいと思います。
若手社員が抱えるキャリア不安とは
ある企業で若手社員向けのキャリア研修を企画していた際、人事担当の方から、こんなことをお伺いしました。
「入社して2~3年経った若手社員が、仕事をし始めて色々と見えてきた今だからこそ『自分はこのままで良いのか?』というキャリア不安を持っている。それは当社で目の前の仕事に取り組むことを当たり前にできている人には少しわかりづらい悩みなのかもしれない」
この話を聞いたとき、私自身「若手社員の気持ちを本当に理解できているだろうか?」と、ハッとしました。
この話をきっかけに、さまざまな企業様と若手社員のキャリア不安についてお話させていただきましたが、以下のようなキャリア不安があるようです。
自身の成長、キャリアの積み上がりに関する不安
- 入社後、頑張ってきたが、成長してきているのか、キャリアが積み上がってきているのか、わからない(成長実感の不足)
- 今の会社で成長しきった感じがして、これ以上の成長イメージが持てない、キャリアが拡がっていく自信を持てない(成長期待の不足)
- 今の会社での成長が、市場価値につながっているのかわからない、自信が持てない(成長期待の不足)
今の会社が自分に合った場所なのか?という不安
- 自分の個性や強みを活かして働きたいが、今の環境が本当に合っているのか不安
- もっと自分に合った職場があるのでは?と迷いが生じる
自分が目指したいキャリビジョンがわからない、本当に目指したいのか確信が持てない
- 明確なキャリアビジョンを持って仕事をしたいが、自分のキャリアビジョンがわからない
- 研修でキャリアビジョンを描いてみたが、しっくりとこない、本当に目指したいのか自分でもわからない
若手社員のキャリア自律を後押しするポイント(若手社員向けキャリア自律研修)
上記のような若手社員に対して、研修として、どのように支援していけるとよいか考えていきたいと思います。
「成長してきた自分と、これからも成長していける自分」に自信を持つ
現場で一生懸命仕事をしている若手社員に、いきなりキャリア自律の重要性や正論を伝えても、気持ちがついてこないことが大半です。上手くいくこともあれば、上手くいかないこともあり、何とか期待に応えようと取り組んでいるが、なかなか手応えや成長実感を得られない状況もあったりします。
だからこそ、未来を考える前段階として、これまでの経験から成長してきたことを認識してもらい、成長できた自分や、今後も成長していける自分に自信を持ってもらうことが大切です。
そして、成長を実感してもらう際には、
・成長には、横(スキル・知識)の成長だけでなく、縦(視野・視座・視点、器)の成長もあり、どちらも重要だと知る
・横(スキル・知識)の成長だけでなく、縦(視野・視座・視点、器)の成長もしてきていることを認識したり、双方のバランスが大事だと認識する
例:相手の状況や感情に配慮した報連相ができるようになった。先輩の気持ちや葛藤も理解できるようになり、一緒に取り組めるようになった
このような深みのある成長実感をしてもらえるような場をつくることが重要になります。
慶應大学の花田先生は、自分ができていない点、認めたくない自分、不都合な真実を抱えながらも自己受容し、それでも一歩を踏み出して行動していくことがキャリア開発のスタートになるとおっしゃっていますが、私自身は、成長実感や未来に向けた成長への自信が、自己受容して一歩を踏み出すエネルギーになるのではないかと思っています。
当たり前かもしれませんが、過去から現在までで積み上げてきたことを確認し、未来に向けてどのように自分のキャリアの可能性を拡大していくか、という流れが重要です。
「業務を覚えて対応できる」から「価値を提供する」に転換する
入社して一定期間を経て仕事を覚えてきたタイミングになると、「担当業務を覚え、ある程度一人前になって成長しきった感があるが、このまま今の仕事をしていて良いのか?」と感じる若手の方がいますが、そのようなモヤモヤを感じる方には、次のステージに上っていく支援が重要となります。
具体的には、担当業務を覚えて自分のやり方や自分にできる範囲で対応するレベル(プロダクトアウト的発想)から、仕事の関係者や顧客が本当に求め、期待していることを理解し、その期待を超えて相手が嬉しく思う、価値だと感じる仕事のレベル(マーケットイン的発想)への転換です。
もちろん担当業務を覚えて対応すること自体も価値ある仕事ではありますが、「自分にできることで対応する仕事」と、「相手の期待を超えていく仕事」が違うことを理解してもらい、改めて自分が何を求められ、何を期待されているのか?その期待を超える価値提供ができているのか?という視点で内省を促します。すると多くの方が、自分がまだまだ挑戦できることを知り、未来への成長やキャリアの拡がりを感じるようになります。
また現場では、この「価値を提供する」という楽しい体験を渡し、熱中して取り組めるような支援をしていきます。
すると、誰かから与えてもらうのを待つ意識から、価値提供のために自ら学ぶ、自ら成長するサイクルに入っていくように感じます。
キャリアビジョンを描くこと重視ではなく、キャリア開発につながる日常行動を大切にする
新卒採用面接でも、MBOにおいても「あなたはどうなりたいか?あなたのキャリアビジョンは?」と、キャリアビジョンを明確化し、逆算させるキャリア論を前提にしすぎていないでしょうか。キャリアビジョン重視型で成功される方もいるので、間違いではないのですが、この考え方だけに傾倒しすぎるのは危険です。
そもそもVUCAの時代で明確なキャリアビジョンを持ちづらい環境ですし、この考え方だけを正にしてしまうことで、自分はキャリアビジョンを持ててないと悩んで行動が止まったり、キャリアビジョンに過剰に固執して行動の幅、キャリアの可能性を狭めてしまったりなど、未来に向けたキャリアの拡がりが狭まってしまうことがあります。
ではどうすればよいかというと、プランドハップンスタンス型のキャリア開発の実践です。
キャリアのために生きると意気込んで、キャリアビジョンを描いてガチガチに計画して行動するキャリア開発ではなく、キャリアの8割は偶然な出来事によって作られるという前提を理解することから始めます。また、キャリアは偶然だからと受け身になるのではなく、キャリアチャンスを引き寄せられるように、掴めるように、自身の興味関心も大切にしながら、プロセスには柔軟性を持たせながら、未来に向けて積極的に自身の土台を作っていくようなプランドハップンスタンス型のキャリア開発が、自身の可能性を拡げていくことを理解していただきます。
例えば、最初は自分にとって面白いとは思えないような営業アシスタント的な仕事だったとしても、
・自分が貢献できる領域を作ろうと頑張り、その領域で成果を出し、自分の役割を確立する(Mustに向き合い、信頼を積み上げる)
・組織からの期待(誤字脱字のない正確性の高い資料作成)に応えるための成長にも向き合うが、それだけではなく、自身の将来に向けて大事だと思う論理性が磨かれるように取り組む(個人視点のCanも開発)
・粛々と対応するだけでなく、自分の興味関心(相手にぱっと伝わるデザイン・コンセプチュアルな見せ方)を仕事に盛り込み、その仕事に自分なりの面白さを作り込んでいく(自身のモチベーション開発)
・上記の実践の中で、新たな挑戦ができるだけの信頼・土台(Can)を積み上げ、自分の興味関心も拡げ、キャリアの可能性を拡げていく
まとめると、キャリアビジョンを鮮明に描くことがキャリア不安を軽減するのではなく、
上記のような日常的な実践や積み上げが、キャリア不安を軽減し、キャリア開発につながっていくという認識を促すことが重要です。
ある企業様では、納得感を更に高めるために、キャリア研修で先輩社員にキャリアストーリーを語ってもらうセッションを設けていますが、とても有効なアプローチです。若手社員がプランドハップンスタンス型のキャリア開発に対して、具体的な実践イメージを持つ機会になります。
若手社員のキャリア自律を後押しするポイント(仕組みとしての支援)
以下では、研修という節目だけでなく、多面的に、日常的にもキャリア支援していくことを考えていきたいと思います。
フラットで気軽に話せるキャリア対話の機会をつくる
弊社でもキャリアプロジェクトメンバーが、キャリア対話会を定期的に開催していますが、人事面談や上司面談までお願いするのは気が引けるが、ちょっとしたモヤモヤを共有したい、やりがいを感じた仕事を共有したい、みんながどんな仕事をしているか知りたい、前向きに仕事をするきっかけがほしい、といった方々が、気軽に参加してキャリア対話できる場になっていると感じます。日常は、業務ミーティングや仕事の対応で視野が狭くなり、いっぱいいっぱいになりやすいかもしれませんが、業務を離れた真面目な雑談の場があると、周りから刺激をもらい、ちょっとした振り返りにもなり、主体的に頑張っていこうと思えるきっかけになります。
キャリアカフェでも良いですし、同期とのリフレクションミーティングでも良いですし、斜めの関係性を作るメンター制度でも良いかもしれません。
業務を離れた、フラットで気軽に参加できるキャリア対話がポイントとなります。
個人に深く向き合い、支援する機会をつくる(人事やキャリアコンサルタントとの個別面談など)
研修やキャリア対話会などだけでは、サポートしきれない人・状況もあるかと思いますので、必要に応じて人事側から働きかけて個別でキャリア面談を実施したり、節目のタイミングで人事とのキャリア面談を実施し、1対1で向き合い、キャリア自律を後押ししていくことも重要です。その際、ただ傾聴して、ガス抜きするだけでなく、本人の成長やキャリア開発を願って、キャリア自律の意識・行動転換を後押ししていくような踏み込んだかかわりも重要となります。
以上、概略ではありますが、若手社員のキャリア自律を後押しするポイントをお伝え致しました。
具体的にどのようなキャリア自律研修を設計していけるとよいのか、人事としてのどのような仕組みを作っていくべきか、などご相談事項がありましたら遠慮なくお声がけいただき、貴社にフィットした施策を一緒に模索させてください。
本コラムが、貴社におけるキャリア自律施策の推進の一助になれば幸いです。