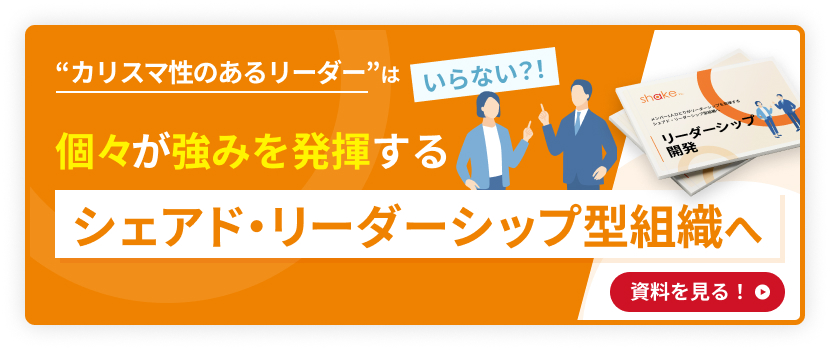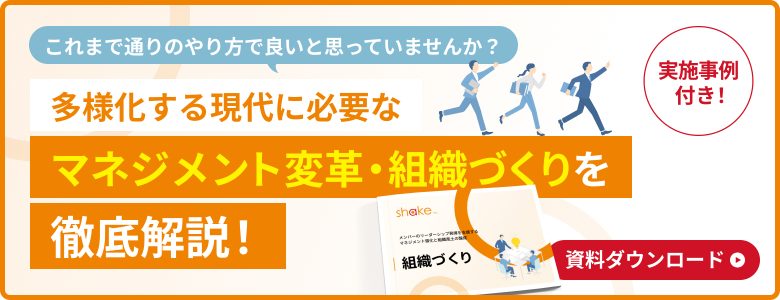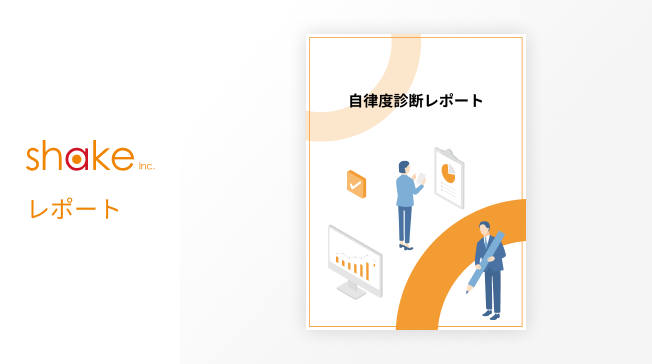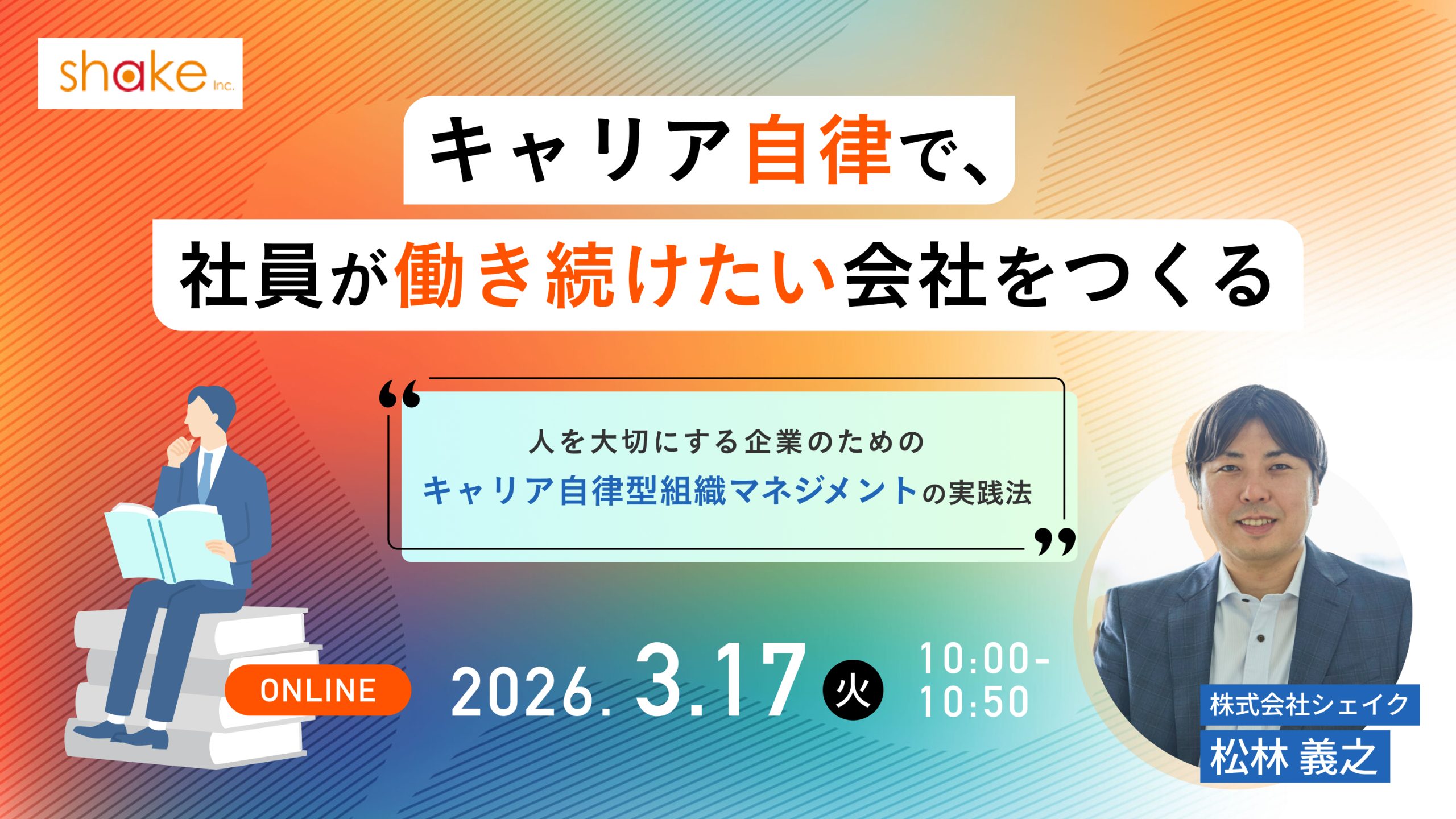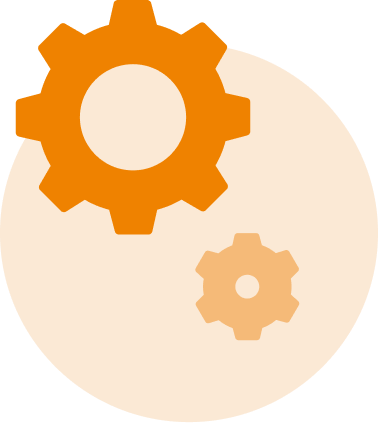こんにちは。シェイク秋山です。
「若手社員にもっと主体的に動いてほしい」「言われたことはしっかり行ってくれるが、言われたこと以上のことをしてくれない」など、若手社員の主体性発揮を求める企業・組織が増えています。
一方で「言われた業務はきっちりとやります」「明確に指示をもらい、業務を完遂したい」という若手社員の方も多いと思います。
では、近年の若手社員は「主体性」を発揮したくないのでしょうか?
そもそもなぜ主体性が必要なのでしょうか?そして、どうしたら若手社員の主体性を引き出すことができるでしょうか?
本コラムでは、仕事における主体性について紐解いていきたいと思います。
主体性とは
主体性とは、自ら意思を持ち、自らの判断で行動し、その結果に責任を持つ態度や性質を指します。経済産業省も人生100年時代の社会人基礎力に必要な要素として主体性が大切であると提唱しており、注目されている能力のひとつです。
「主体性」と混同されがちな言葉に、「自主性」という言葉もあります。
辞書(※三省堂『大辞林 第三版』)によると、「自主性」は「自ら進んで物事を行う性質や態度」と説明されています。決められた枠組みやルールの中で発揮される行動力とも言えるかもしれません。例えば、「毎月〇〇回、顧客を訪問する」という目標を遂行する際に訪問回数を増やしていくのは自主性といえます。
一方で、「主体性」という言葉を辞書で引くと「自分の意志や判断で行動し、その結果に責任を負う性質」と説明されています。訪問の目的が「受注」だとすれば、どのように工夫すれば成果につながるのか?自ら考え、実行に移す力など、本質的な部分に関わるのが主体性と言えるでしょう。
主体性が発揮されていないと指示待ち型の行動になりがちです。「何をすればよいかわからない。指示がなければ動けない」といった状態では、自ら仕事を推進することが難しくなりるとともに、「~しなければならない/やらされている」という思考に終始し、仕事の面白みややりがいを感じる機会が減少してしまうのではないでしょうか。
人生の中で仕事に費やす時間が長いからこそ、イキイキと働くことが人生の質に影響すると考えます。そのためにも、主体性を育み、引き出すかかわりが大切です。
若手社員の主体性を妨げる理由
- 指示待ち文化: 企業やチームの文化が「指示命令型/マイクロマネジメント型」であると、若手社員は自分から積極的に行動することを躊躇することがあります。上司や先輩が細かく指示を出し、手取り足取り教える環境では、若手社員は自分で考え行動する機会が少なくなり、主体性が育まれません。
- 失敗を恐れる環境: 若手社員が失敗を恐れて積極的に意見や提案をしない場合があります。特に企業やチームの文化が「失敗を許さない」「ミスをすると評価が下がる」という風潮であれば、若手社員は自己主張を控え、消極的になりがちです。
- コミュニケーション不足: 上司や先輩とのコミュニケーションが不足していると、若手社員は自分の意見や考えを伝える機会が少なくなり、主体的に行動することが難しくなります。また、フィードバックや相談の場が少ないと、成長やチャレンジの意欲が薄れてしまうことがあります。
- 業務の範囲が限られている: 若手社員に任される仕事がルーチン的な作業や限られた範囲に留まっている場合、主体性を発揮する機会が減少します。自分の意見やアイデアを活かせるような仕事が与えられなければ、自然と主体性は低くなります。
- 評価制度が不明確: 主体性を重視する評価制度がない場合、若手社員は「積極的に行動しても評価されない」と感じ、主体性を発揮する意欲が低下することがあります。評価基準が曖昧であったり、上司の目に触れる機会が少なかったりすると、自分から主体的に動くことへのモチベーションが湧きにくくなります。
- 組織の階層構造: 上下関係が強調される組織では、若手社員が意見を出しづらくなることがあります。自分の考えを上司に反対されるのではないかという不安や、年齢や経験が少ないことへの遠慮が、主体性を抑制してしまうことがあります。
このように、様々な要因があることがわかります。本人の仕事に対する捉え方だけではなく、企業や組織全体の文化や環境を見直したり、若手社員が自分の意見やアイデアを積極的に表現できるような風土を作ることも重要と言えそうです。
若手の主体性を育むための鍵①:目的意識
主体性は、持ってうまれた素質や個々の性格によるのではないか?とお考えになる方もいらっしゃると思いますが、主体性は後天的に育むことが可能です。
そのためには、以下のように仕事の目的を多角的に理解することが有効です。
- 顧客の視点
顧客が目指すゴールを理解して、顧客のために何ができるかを考え行動することが、結果的に顧客の貢献につながるとともに、主体性の発揮につながるでしょう。
仕事の目的を自分に与えられた仕事を遂行するに置くのではなく、顧客の目的や目指しているゴールを共に考え、達成することに置くことを促しましょう。価値創出に向けて今の自分にできることを考え、行動するなど、顧客に目を向けることが、個人が主体性を発揮するきっかけとなります。 - 組織の視点
自身の担当する仕事は会社や組織にどのように貢献しているのか?を考えまることで、仕事に取り組む幅が広がることがあります。貢献とは、もしかしたら売上かも知れませんし、顧客への価値提供を通じて自社のプレゼンスを高めることかもしれません。
自身のチーム貢献を考え、ともに働くメンバーを助けたいと思えば、自然と自身の目の前の仕事だけでなく、他者の仕事への興味関心が広がり、結果としてアクションもおのずと変化するでしょう。 - 自分の視点
この仕事が、自身のキャリアにどう紐づいているかを考えることも大切です。
例えば、今の仕事が今後挑戦したい仕事に向けた最初のステップであるととらえると、顧客や組織のためだけではなく、仕事を通じた経験が自分自身のためにもなると腹落ちし、さらに挑戦や積極性を引き出すでしょう。
※キャリアに関する考え方については、
こちらの記事も是非読んでみてください:(https://shake.co.jp/news/240814/)
他にも、環境や社会の視点など、より広く、目の前の仕事がどのような目的で行われ、なにに役立っているのかをとらえることも有効であるといえますが、
まずは、顧客、組織、自分の視点で考えることからスタートできるとよいでしょう。
若手の主体性を育むための鍵②:仕事の渡し方
- ストレッチな仕事に挑戦する機会の提供
主体性が芽生える最初のステップは「ストレッチな仕事に挑戦する機会」です。例えば、新たなプロジェクトの責任者に抜擢されることや、これまで経験したことのないタスクに挑戦することが挙げられます。
「頑張れば達成できる」難易度の設定や、「達成まで支援が受けられる」といった環境づくりを上司や周囲の方は心掛けてください - 目的について共通認識を持つ
若手社員の意向を理解し、その仕事が本人のキャリアや成長にどんな影響、能力開発をもたらすものなのか?を本人視点で伝え、共通認識を持つことが大事です。
今の仕事を通じて獲得するであろうスキルとその応用の可能性を伝え、スキルの蓄積がキャリアの可能性を広げることを若手社員に伝えていきましょう。共通認識を持つためにも、日頃から若手社員の意向や考えをキャッチアップすることが重要です。 - 期待役割を明確にする
チーム内での自分の役割が明確であることも重要です。何を期待されているのかを理解し、腹落ちすることが大切です。また、期待の背景(所属する組織のチームのミッションや目標、課題など)を知ることも重要です。
これらの要素を通じて、個々の価値観やマインドが変化し、主体性が醸成されていくでしょう。
若手の主体性を育むための鍵③:心理的安全性
- 失敗を許容する文化の醸成
皆様の職場では、失敗を責めるのではなく、学びの機会として捉える風土はあるでしょうか?
万が一、失敗した際には、挑戦に対する承認とできたことにも着目しポジティブなフィードバックも行いましょう。
そのうえで、共通の目的(顧客や組織、自身のキャリアなど)の視点から課題をフィードバックし、今後に向けたアクションを共に整理することで、安心して行動できる環境を作ることができるでしょう。 - 傾聴をもとにした発言しやすい場づくり
誰もが自分の意見を言え、上下関係や立場に関係なく対話できる場を設けることで、主体性が発揮されやすくなります。
そのためにも、年齢や立場構わず傾聴の姿勢を意識し、意見やアイデアに対して感謝や関心を示すことで発言しやすい雰囲気を作ることが重要です。 - 成長や役割期待に対する課題のフィードバックを恐れない
心理的安全性の高い組織とは、自分にとって耳の痛いことを言われない、チャンスフィードバックがない組織ではありません。むしろ、本人や組織が目指す姿に対して建設的なフィードバックが日常的に行われる環境では、心理的安全性が高まりやすくなります。
若手に対して明確な役割や期待を伝えると同時に、行動を支えるリソースや支援体制を用意しておくことも重要です。「いつでも相談していい」というメッセージを繰り返し伝えながら、困難に直面しても安心して頼れる環境を整えるとともに、支える側も待つだけではなく、定期的に状況を聞きにいくなどのコミュニケーションが重要になります。
主体性を育む研修の有効性
日本では以前から現場での育成(OJT)が重視されており、「主体性といったスタンス」は研修で学ぶものではなく、現場で身につけていくべきものだという考え方があります。
主体性といったスタンスやマインドを現場任せにしてしまうと、上司の育成力や育成方針、職務内容等によって大きくばらつきが出る可能性があります。
また、人事として育成したい人材を最終的に育成できない可能性もあります。
人事戦略に基づいた人材育成のためにも育成を現場だけに頼らずに、人事として責任を果たすべきであり、研修はその一つの方法と言えます。
ここからは、具体的な研修例について、ご紹介できればと思います。
主体性を目的とした研修内容の例
- 実践演習型シミュレーション演習
主体的に行動するために「問題発見解決」の考え方と「自ら周囲に働きかけ、動かす」ための具体的行動を学び、リアルなビジネスシーンを題材にした実践シミュレーションを通して自身の主体的行動における課題を認識し、職場で実践すべき具体的な行動を体感します。
実際の仕事に近い状況設定の中で、研修を「インプット/ディスカッションする場」だけなく、実践を伴う「逃げ場のない自己客観視」の場とし、職場での行動変容のイメージをわかせます。 - フィードバックセッション
シミュレーションやロールプレイングを研修に取り入れながら、研修での行動に対する具体的なフィードバックを受けることで、続けることと新たにやるべきことを明確にし、主体的な行動を自ら決めることも有効です。
また、360度サーベイ(多面評価)を取り入れ、現場での行動の自己客観視の場面を作り、具体的な課題設定を行うことも有効でしょう。
主体性を目的とした研修における重要なポイント
研修が成功するためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 研修前実践的な内容
受講者の強み・課題を現場や上司からヒアリングし、各組織における主体性とは何かを明確にします。そのうえで、受講者のあるべき姿を設定し、研修の入り口(研修前の受講者の状態)と研修の出口(研修終了後の理想の状態)をもとに研修設計を行いましょう。 - 研修実施
研修実際の際は、受講者の発言やアウトプット、グループディスカッションの内容から主体的に「なれない」理由や背景を事実ベースで捉えるようにしてください。本人要因だけでなく、環境要因(周囲からの支援や上司側の課題)を検証し、必要に応じて手を打ちます。 - 研修終了後
研修で学んだ内容を実務に活かすためには、フォローアップセッションを設けることが効果的です。例えば、定期的な振り返りや目標設定の仕組みを導入することも、主体性を継続的に育むことに寄与します。
主体性が高まった具体事例
シナジーマーケティング株式会社様での導入事例
自ら考える営業力を育成する、継続的な若手育成メソッド―論理的思考力×実践トレーニングで実現する、提案型営業への転換―
https://shake.co.jp/works/synergy-marketing/
「シェイク研修で相互フィードバックを多く行ったことで、同期同士でのフィードバックができるようになりました。1回目のグループワークでは、ぎこちない雰囲気で相手への意見も遠慮がちでしたが、回を重ねるごとに、ビジネススキルとして相互にフィードバックができるようになっていました。「○○さんの○○はすごいよね」というお互いを認め合うような対話が自然となされ、同期としての結束力が培われていると感じました。」
上記のように、フィードバックのような難易度の高いビジネススキルに関しても、研修内で取り入れることで日常的に活用され、主体的に自身や相手の成長や課題に向き合う力が培われていきます。
まとめ
個人の主体性は組織のパフォーマンスを大きく左右する重要な要素です。また、若手社員の主体性を育むことは、行動における判断力を養い、結果に責任を持つことで、仕事のやりがいを感じるとともに、自身の成長を実感することができるのではないでしょうか。
研修を活用し、個々の目的意識を高めることで、主体性を組織全体に根付かせることが可能です。
シェイクでは具体的な育成施策の策定や研修設計、研修後のフォローアップ体制も含め総合的にご支援しています。
下記に参考資料をまとめておりますので、よろしければご確認ください。