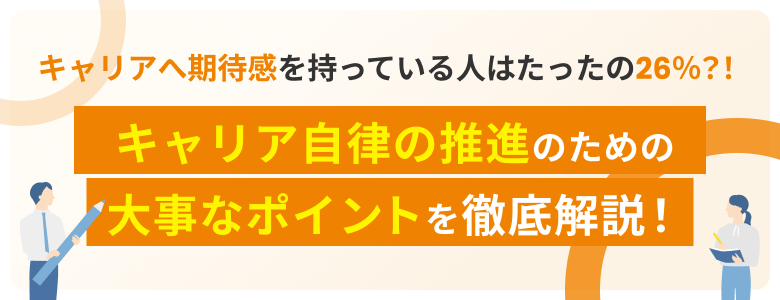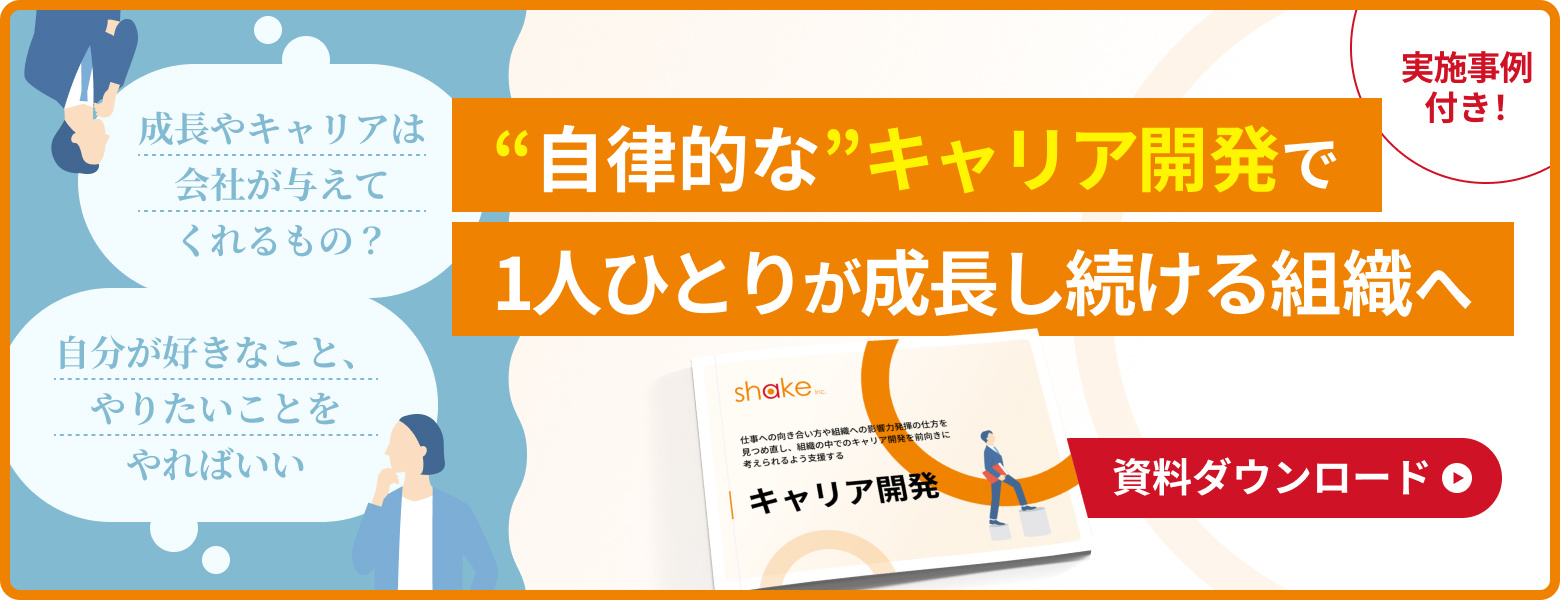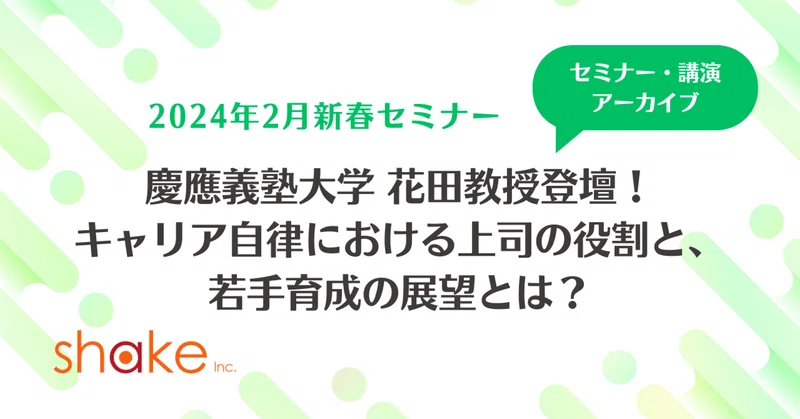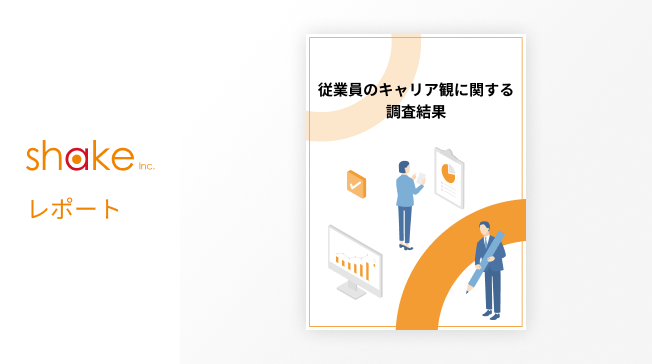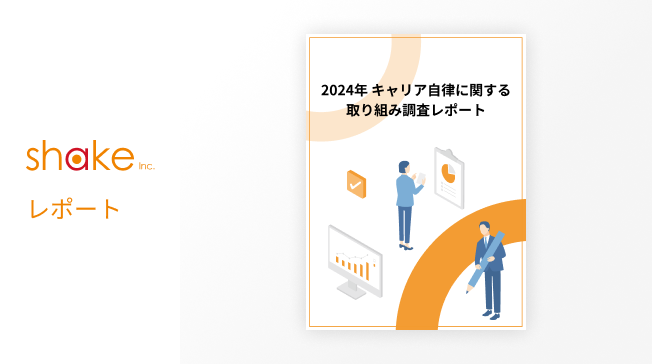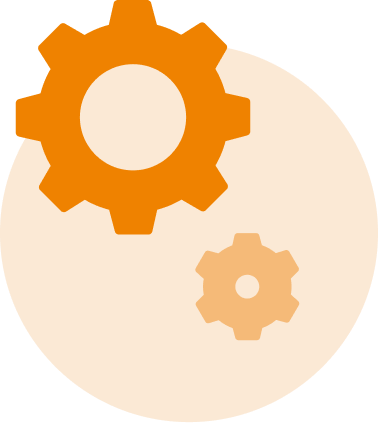皆さん、こんにちは。シェイク松林です。
今回のキャリア自律コラムのテーマは「働く居場所」を自ら作るというキャリア開発です。
突然ですが、皆さんは、自社に自分の居場所があると感じられていますか?
自社の若手・中堅・シニア、管理職の方々は、自社に居場所があると感じていると思いますか?
私は、これまでシェイクでお客様へのソリューション提案やプログラム開発を行ってきましたが、
今の役割を継続するだけだと自分の居場所がなくなるのではないか?自分の居場所は今の役割ではないのではないか?と、
会社や上司から言われたわけでもないのですが、自分の意識として感じてしまうことがあります。
働く居場所とは、職場で自分の仕事や役割を作れているという実感や、
周囲からの期待に応え、お役に立てている実感、
また、それらに対して自分がやりがいや安心を感じられている状態のことを言いますが、
誰しもこの自分の「居場所」について不安感や満足感を感じた経験があるのではないでしょうか。
人によっては自分の居場所を感じられずに、居場所を提供してくれない会社や上司に他責になってしまったり、
最低限の仕事ができれば良いと自身のキャリア開発を諦めてしまったり、場合によっては離職してしまったりと、
職場に居場所を作れないが故に、ネガティブなサイクルに入ってしまう人もいるように感じます。
我々キャリア自律の推進者は、「社員全員」が働く居場所を
感じられるようなキャリア支援を行っていく事が役割だと思っていますが、
我々は、この「働く居場所」にどのように向き合っていけると良いのでしょうか?
そのヒントは、慶應義塾大学の花田先生の著書『働く居場所の作り方』にあります。
今回のコラムは、同書籍を参照しながら、キャリア自律を考えていきたいと思います。
※書籍『働く居場所の作り方』は、1人ひとりが、自分の成長・キャリア開発に当事者意識を
持つ重要性を再認識したり、とても勇気づけられる内容ですので、ぜひ書籍もご確認ください。
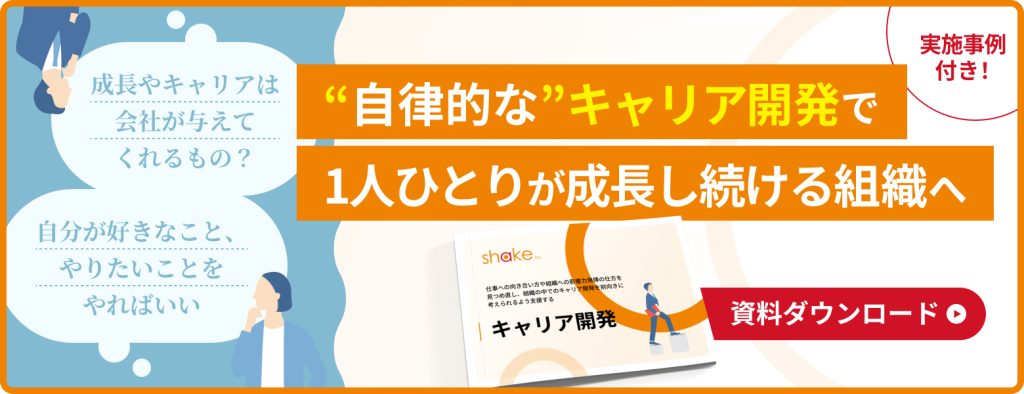
働く居場所とは何か
同書籍では「働く居場所を自ら作り続けることがキャリア開発である」と、「どのような環境下、キャリアフェーズにおいても働く居場所を自ら作り続けることがキャリア自律である」と記載されているように私は捉えています。
では「働く居場所」とは何なのか?
同書籍では、居場所を物理的な居場所ではなく、1人ひとりの認識や精神状態を表す言葉として使われています。
具体的には、会社に自分の役職や座席があるという意味ではなく、
・仕事の役割…職場で自分の能力を発揮できている、自分の仕事や役割を作れている
・人間関係…他者から信頼をされている、職場やお客様のお役に立てている、評価されている
・心の動き…上記の状況に対して、自分が満足している、安心している、気に入っている
といった自身の認識や精神状態を軸にして考える居場所という考え方です。
どうしてもキャリア開発というと、自身の市場価値を高めることや、昇格やスキルアップを求めがちではありますが、上記の「働く居場所」を自ら作っていくことが、「イキイキと働く職業人生、キャリア」を作っていくことなのではないかと思います。
同書籍P84に「スキルの獲得や知識の習得のチャンスはその都度、会社や組織などが新しい仕事の獲得のために提供してくれると思います。しかし、それに向けて自分の心を動かすことに会社も上司も周囲の人も責任をもってくれません。自分が当事者意識をもって対応するしかないのです。」と記載がありますが、私自身、働く個人としてとても共感しました。
会社や上司は動機付けや機会提供を行いますが、会社も上司も人の感情までコントロールすることはできず、最終的に自分の心を動かして対応するかは自分自身であるという考え方。当たり前なことではありますが、どこか会社や上司に求めてしまいがちなことを、自身が当事者意識を持って対応する視点は、とても重要だと感じましたし、我々1人ひとりが、自身のキャリア開発に対して当事者となることが、キャリア自律において1番大事ではないかと感じました。
働く居場所を自ら作るというキャリア開発とは
では、働く居場所をどのように作っていくのか?
同書籍では、自己実現ではなく個性化の重要性が説かれています。
(キャリアビジョンに自己実現目標を置かなければならないという意識や、自己実現の達成が何よりも大事といったように、過度に自己実現に囚われてしまうと、最短距離や目の前の経験の要否を考えてしまい、本来自分が持っている可能性やチャンスを閉ざしてしまうのではないかという指摘)
自己実現重視型のような目標に向けて一直線に向かうキャリア論ではなく、
多様な可能性を持つ自分であるという認識を持ち、自身の多様な可能性を拡げ続け、自分らしさを追求し続けていく「個性化」というキャリア論です。
では、具体的に個性化とは何なのか?どのようなプロセスが重要なのか?を私の理解も交えて記載します。
個性化とは?
個性化とは自分らしさの連続的な追求である。
また個性化のためには、以下のようにそれぞれのキャリアステージでの基礎基本を獲得し、自分らしさを付加していくプロセスが重要であると記載されています。具体的なステップを以下に記載します。
1.基礎基本を習得し、業務ができるようになる
新たな職場や、新たな業務に就いた際に、自身が担当する業務を覚え、その業務を対応できるようになることがファーストステップです。
自分らしさを出すのは基礎基本をマスターした後というわけではなく、並行して行えば良いと思っていますが、基礎基本をマスターしていない中で、自分らしさだけを主張しても、なかなか成果や貢献につながらないことが多いです。まずは業務を覚え、遂行できるようになることに向き合うことが重要です。
この段階は、会社としての顧客への価値提供のプロセス機能を担うことができるようになるという段階です。
2.業務を自分の仕事にする
次の段階は、業務をマスターして対応するという段階から、自分らしさを付加していく段階で、業務に対して自分なりの興味関心・好奇心を発揮して、業務をオンリーワンの自分の仕事にするという段階です。
例えば、ビジネスライクではなく人と人との関係性を大事にしたいという価値観や、人はどうしたら主体的に動くのか?に興味関心を持っている営業職の場合、そのような自身の価値観・興味関心を営業という業務の中に盛り込んで、自分らしい営業という仕事に作り上げていくというイメージです。お客様が会社としてスポーツチームを持っていたら一緒に応援に行ったり、お客様の興味関心、モチベーションの源泉を知ろうと興味を持って聞いたり、自分の興味関心との共通点を探ったり、ちょっとした面白いことを言い合えるような関係性を自ら作っていったりなど、営業という標準の業務から自分らしい営業の仕事を作り込んでいくイメージです。
ステップ1の業務マスターをしたら、この会社で成長し切ったと感じる方や、刺激を感じられなくなってしまう方もいますが、次の段階があることを伝え、気づいていただくことが重要となります。
3.自分の仕事をお客様への価値や組織貢献につなげる
次の段階は、自分らしい仕事で対応することを目的とするのではなく、お客様や組織の期待を超える価値提供をすることに真摯に向き合う段階になります。時には自分らしさではないやり方に向き合う必要がある場面もあるかもしれませんが、期待を超える価値提供に向き合うことで、自身の幅も広がり、また相手から頼られ、お役に立てている実感を持てるようになり、自分なりの居場所を確立していくことに繋がります。
1~3のプロセスを経ると、自分の仕事や役割がある実感、他者に求められ、貢献している実感を持てるようになり、心理的な居場所感を感じられるようになります。
4.1~3を回し続け、新たなキャリアステージ、居場所を作り続ける
上記1~3を1サイクルとした場合に、1度、自分なりの居場所が作られると、そこで安住してしまうこともありますが、1~3を回し続けることが重要です。
今の役割や活躍の仕方をそのまま続けていても、自分には居場所がないのではないか?と私自身も感じることがありますが、自分から新たなキャリアステージを作っていく、新たな居場所をつくっていく挑戦をしていくことが重要です。そして、この連続がキャリア自律の実践であり、イキイキと働くことではないかと思います。
おわりに
本書籍を読んでの改めての気づきは、働く居場所感を感じ、イキイキと働くためには、個人視点だけでは不足していて、個人視点と組織視点の統合が重要だという点です。
イキイキと働くことを考えた際に、組織視点を排除し、個人視点重視で生きることが語られたりもしますが、自分のことだけを考えていても居場所感は感じづらく、お客様や組織のニーズにも向き合い、そこに応えていくからこそ、居場所感を感じ、イキイキと働けるという点はとても重要な視点だと感じました。
皆さんの会社の社員は、ステップ1~3の段階を登ることができていますでしょうか?
ステップ1~3を登るうえで課題になっている点は何でしょうか?もしかしたら、その点がキャリア支援のポイントかもしれません。
またステップ3まで至った社員が、ステップ4に入り、次のキャリアフェーズに移行するのは、どのようなタイミングでしょうか?
そこが年代別キャリア研修を打つべきタイミングかもしれません。
現在、シェイクとして、上記のような働く居場所を自ら作るという思想も盛り込みながら、キャリア自律研修の設計をしています。
改めてになりますが、我々のようなキャリア自律の推進者は、「社員全員」が働く居場所を感じられるようなキャリア支援を行っていくことが役割だと思っています。
今後も、キャリア自律の取り組みを共に進化させていけたらと思いますので、共に探求して下さる方がいれば、遠慮なくお声がけください。
本コラムが、貴社におけるキャリア自律施策の推進の一助になれば幸いです。