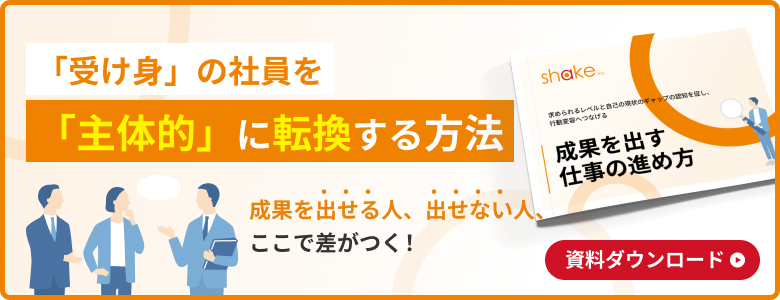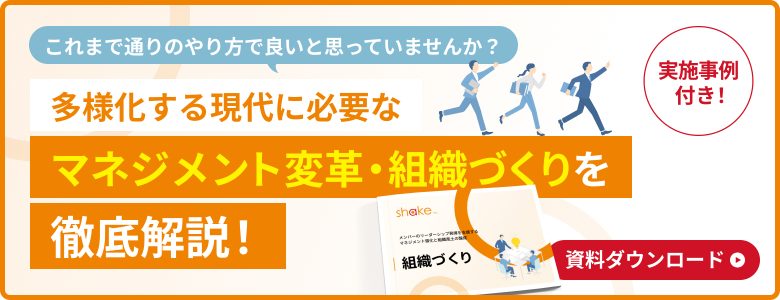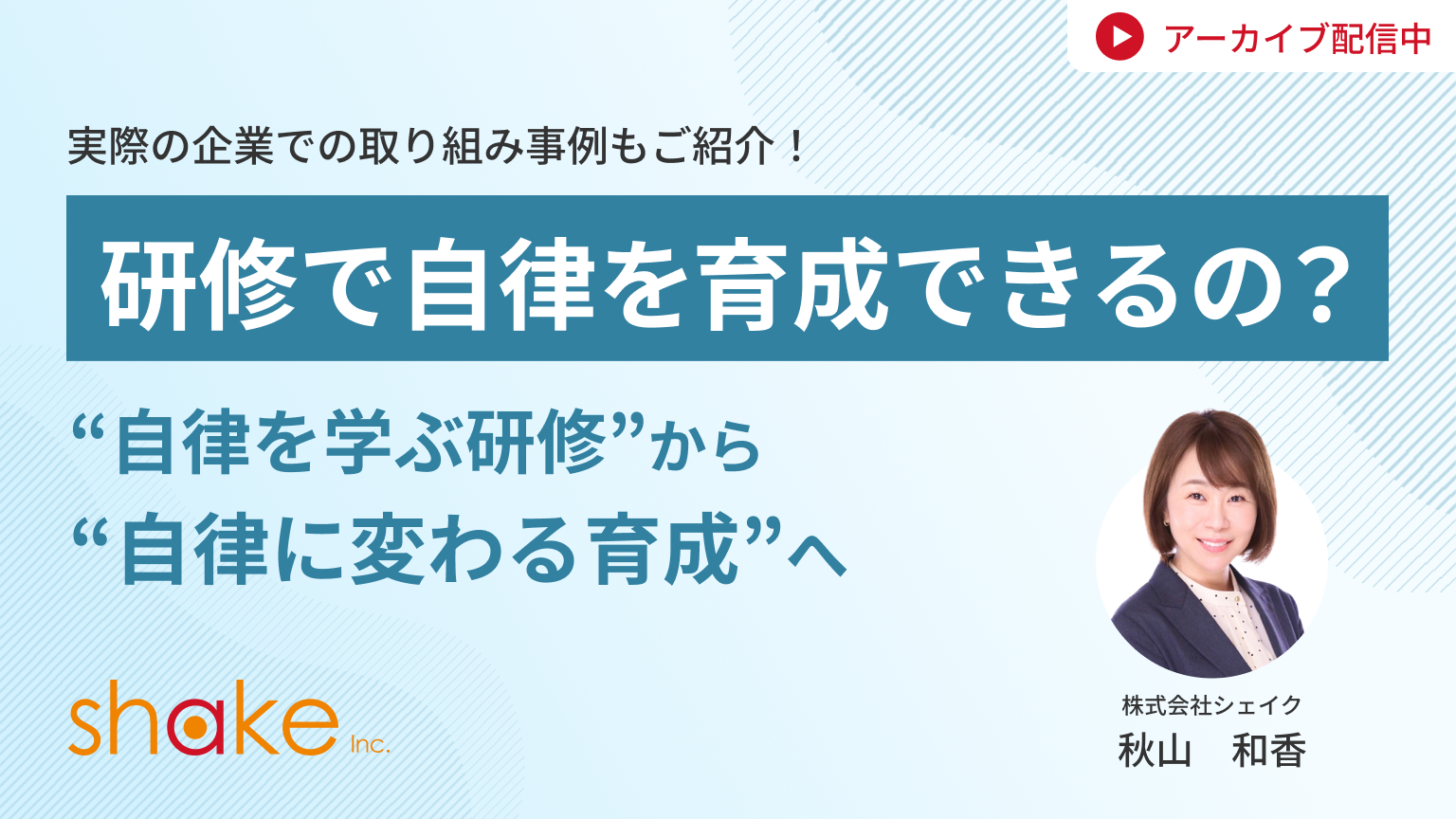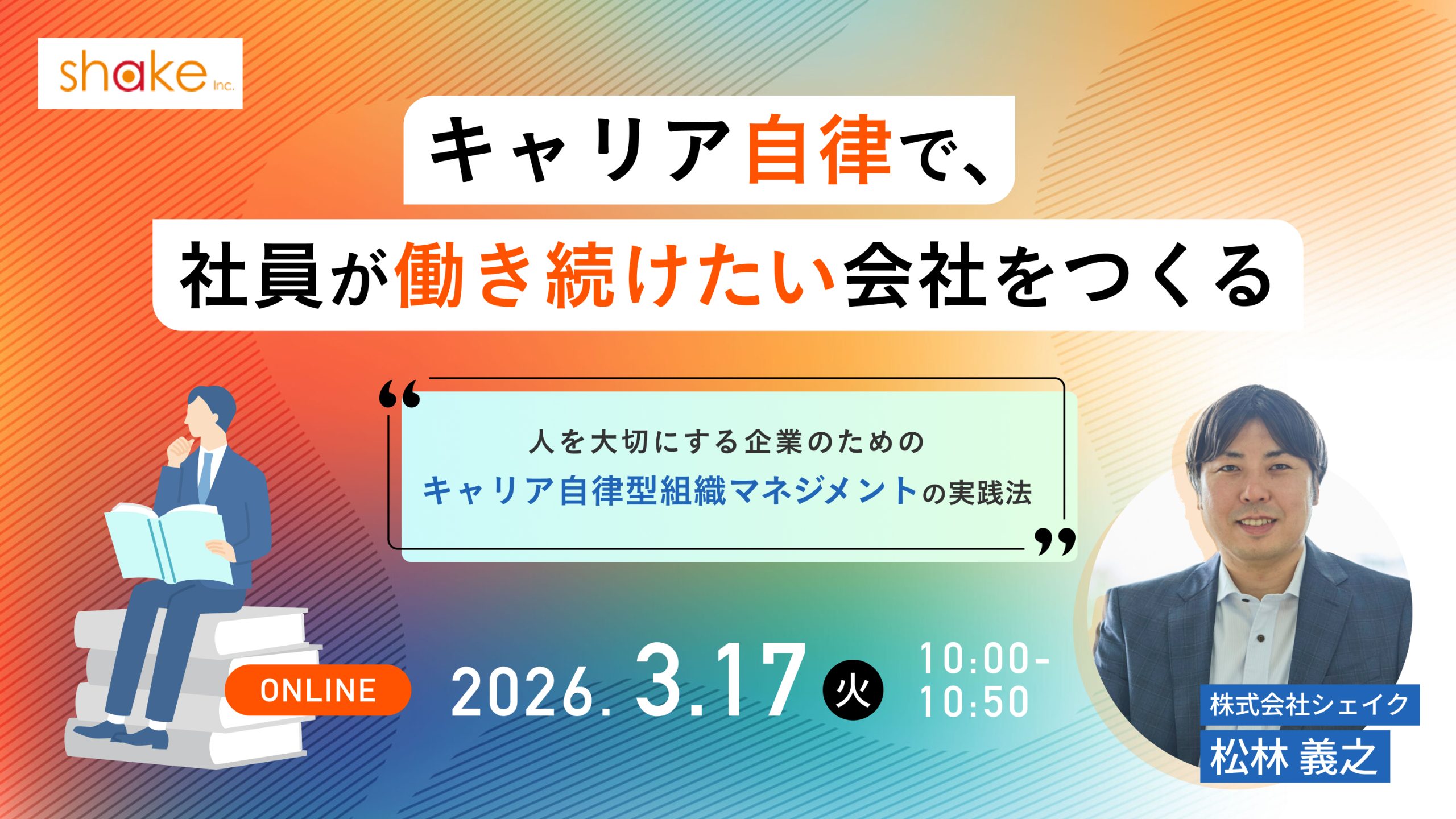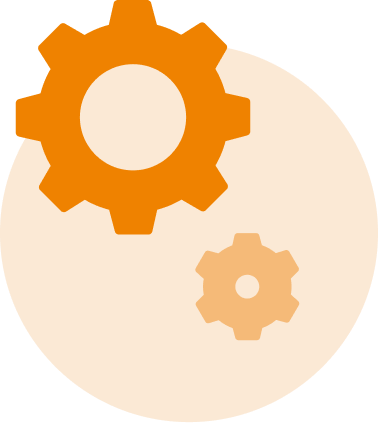こんにちは、シェイク飯島です。
近年「自律型人材を育成したい」という相談が増えています。
背景には人材の定着率の低下や若手の育成に関する課題感、管理職のマネジメント負荷の高まりなど、組織を取り巻くさまざまな状況があると考えられます。
今回は自律型人材育成に関して改めて考えていきましょう。
なぜ今、「自律」が求められるのか?
企業が直面する「自律型人材不足」の課題
弊社は20年近く、「自律型人材の育成」の重要性を訴えてまいりました。近年は特に、働き方の多様化や市場の変化が加速する中で、「指示を待たず、自ら考え、行動できる人材」 の必要性が高まっていると感じます。
なぜ自律型人材が求められているのでしょうか?
社会環境の変化、生成AIの影響など様々な視点がありますが、今回は「管理職の罰ゲーム化(多忙で負担の多い管理職)」の視点から考えてみましょう。
組織においては、かつては管理職(上司)が方針を決め、仕事を指示し、部下がそれに従って動くというスタイルが一般的でした。しかし現在は、変化のスピードが早く、管理職がすべてを把握・指示するのが難しい時代です。また部下となる若手・中堅層の価値観も変化し、指示命令で動くことを好まない方が増えています。
管理職自身も、プレイングマネージャーとして業務とマネジメントを両立する状況にあり、部下1人ひとりの状況を把握し、的確な指示をすることも難しくなっています。だからこそ、社員1人ひとりが組織や仕事の目的を理解し、自ら考え、動く「自律型人材」になる重要性が高まっています。
こうした自律型の部下が増えることで、管理職は「指示命令」ではなく「支援・対話」に時間を使えるようになり、組織全体の生産性やエンゲージメントも向上します。
つまり、管理職を孤軍奮闘させないためにも、組織全体で“自律”を育む必要があるというのが、今あらためて自律型人材が求められている理由の1つなのです。
しかし、多くの企業が以下のような課題を抱えています。
- 指示待ちの社員の増加 : 言われたことを最低限こなす「静かな退職」やリスクを恐れてチャレンジせず、確実な仕事だけをやる若手社員などが話題になっています
- 変化に対応できない・変化への抵抗感 : 本来有している能力は高くても、新しい環境や業務に消極的で、リスクに対する不安から行動が止まってしまう傾向が見られます
- 成長期待とエンゲージメントの低下:上記と矛盾しますが、若手を中心として成長意欲が高い、むしろ成長しないと不安を感じる方が増えています。仕事に対する受け身の姿勢が続くと、成長実感や成長期待が低下し、エンゲージメントの低下や離職につながることがあります
このような状況が続くと、組織全体の成長が鈍化し、競争力が低下します。管理職が機能し、組織が成長していくためには、社員一人ひとりが主体的に行動できる「自律型人材」の育成 が欠かせません。
研修で「自律」を促すことの意義
社員の自律を促す方法の一つが「研修」です。しかし、単なる座学研修では行動は変わりません。「学ぶ」だけでなく、「実践を通じて行動変容を促す」 研修設計が重要です。
本記事では、研修を活用して社員の自律を促し、組織全体の変革につなげる具体的な方法 を解説します。
自律とは?ビジネスにおける定義と重要性
自律の定義:「仕事の目的や周囲の期待をとらえ、自ら考え、行動する力」
「自律」とは、単に独立して業務を進めることではなく、組織の目標や周囲からの期待を理解し、自らの判断で適切な行動を取る能力 を指します。
自律型人材は、上司の指示を待つのではなく、「何が求められているか」を考え、自分で行動を決定できる人材 です。
「自立」との違い:「他者と協調しながら主体的に動く力」
「自立」は他の人の助けを受けずに個人が独立して動くことを指しますが、「自律」は自分が決めた規範やルールに従って、自らの行動をコントロールすること。同時に、周囲と協力しながら主体的に動く力 を意味します。
ビジネスでは、「自立」よりも「自律」が求められます。チームで成果を出すためには、周囲と協調しながら主体的に動く力が必要だからです。
企業における「自律型人材」とは?
自律型人材の特徴を、非自律型人材と比較すると、以下のようになります。
| 項目 | 自律型人材 | 非自律型人材 |
|---|---|---|
| 行動特性 | 自ら課題を見つけて行動する | 指示がないと動かない |
| 学習姿勢 | 継続的にスキルを磨く | 受け身で学習する |
| 変化への対応力 | 環境の変化に柔軟に適応する | 変化を嫌い、抵抗する |
自律型人材の育成は、組織全体の成長スピードを高め、競争力を向上させる 重要な取り組みです。
研修を通じて社員の自律を促す実践ステップ
研修前:社員の現状を把握し、目的を明確にする
研修を成功させるためには、「なぜ自律型人材を育成するのか?」 という目的を明確にすることが重要です。
同時に、以下についても明らかにしましょう。
・自社にとって、また受講者の階層における「自律」とは何かを定義する
・現場でどのような行動が生まれていればよいのか?を具体化する一口に自律といっても、現場で求められる行動や姿勢は様々です。社員が学んだことを職場実践するためにも、「現在、どういう行動が求められているのか?今後、どのような行動が求められていくのか?」を押さえた研修、学習内容にする必要があるからです。また、研修前後での実践を行う場合、上司や職場の協力が不可欠となりますので、事前に調整が必要です。
研修前の準備として必要なポイント:
- 社員の自律度の現状把握:自律度診断・360度サーベイなどを活用し、現状の社員の自律度合いや課題を定義。自律を阻害している要因なども把握します。
- 求める行動変容を明確化:「〇〇ができるようになる」など、具体的な目標を設定
- 上司・職場を巻き込む:事前課題で上司から期待を伝えていただく、もしくは、研修後の実践を支援する体制・仕組みを作る
研修中:自律を促す実践型プログラムを導入
研修では、グループワークやグループ討議による学習も効果的ですが、実際に行動を変える仕掛けを組み込むことも重要です。
また、特に若手・中堅社員の場合、自律を目指していても「行動できない」理由があることが多く、単にスキルインプットや個人の意識変革だけでは行動に至らない状況が見られます。
企画側としては、「自律できない、もしくは行動できない」理由の仮説を立て、以下のような側面からもアプローチすることを考える必要があるでしょう。
1. 視座をあげ、組織視点を持つ
「自分が動けないのは、自分のせいではなく“構造”によるものでは?」という視点を提示し、根本的にアプローチすべき組織課題を考えます。アプローチすべき本質的問題が明確になると行動の第一歩が後押しされます。
2. 役割や立場を一時的に変える(関係者視点の獲得)
例えば、弊社のシミュレーションでは、普段の自分とは異なる役割で仕事を体験する中で、他部署連携や上司巻き込みを体感し、「こう考えればうまくいくのかもしれない」という感覚をつかんでいただきます。「いつもと違う視点・役割」から「仕事」をとらえることで、視野が変わり、思考や行動が変わる仕掛けを取り入れています
3. 未来起点のストーリーテリング
現状の課題や障害にフォーカスするのではなく、「未来のこうなってほしい」から逆算して今を捉え直したり、課題を設定していきます。あきらめや無力感が強い場合は、「なぜできないのか?」ではなく、「実現するために何が必要か?」といった未来起点での問いを用いて、考えていくとよいでしょう。
4. 自身の強みを自覚する
課題解決型(できていないところに目を向け、一人前のレベルまで引き上げる)の育成は「社会人としての信頼」を得ていく若手層には必要な育成ですが、個々人の主体性や自律性を伸ばすとは言えない側面もあります。主体性や自律性を伸ばすためには、個々の強みを理解し、それらを行動に反映させていく必要があります。シェイクでは、多面評価(360度評価)を取り入れ、「強みサーベイ」を通して、他者の視点を含めた自己を客観視を行い、強みを認知したうえで、職場での実践につなげています。
研修後:行動変容を定着させる環境づくり
研修後、学びを実務に活かせる環境を整えないと、せっかくの研修が形骸化してしまいます。研修後は、それぞれの成長段階や階層に応じて、職場での実践を行う必要があります。
その際は以下のようなフォローアップ施策が一般的に行われています。
行動変容を促すフォローアップ施策:
- 1on1ミーティングの導入:上司と定期的に進捗を確認
- グループ学習/フィードバックの活用:チームメンバー同士で学びを共有
- 組織課題と研修内容の連携:研修で学んだことを組織や日常業務の問題発見解決に落とし込み、実践活動
研修後の実践で一番重要なことは「職場実践は成功体験を積む場」と定義することです。そのためには、職場実践でのアクションプラン/問題解決で大きな計画やストレッチ過ぎる課題を選ばないことが大切でしょう。研修で学んだからと言って、難易度の高い職場の課題解決は難しく、途中で行動が止まってしまう可能性があります。スモールステップを意識し、最初は自分の仕事や周囲への巻き込みにフォーカスし、徐々に影響力を広げていくイメージで職場実践を設計すること、また周囲の期待調整が必要です。
まとめ:研修を「学び」で終わらせず、自律を定着させるには?
自律型人材の育成は、単なる知識の習得ではなく、行動変容を促し、組織全体の成長につなげる取り組み です。
研修の効果を最大限に高めるには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 研修前:目標設定と課題の明確化(社員の現状を把握し、求める行動変容を定義)
- 研修中:実践型プログラムの導入(ケーススタディやロールプレイを活用)
- 研修後:行動変容を支援する環境づくり(1on1ミーティングや成功体験付与の設計)
これらを組み合わせることで、社員の自律を促し、組織の成長を加速させることができます。